
「離婚したいけど、何から始めればいいか分からない。」
「離婚の手続きはどうしたらいいの?」
「離婚するまでに、何を話し合って決めたらいいの?」
そのような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?
相手方と話し合う前に、離婚を考えた方が知っておくべき基本的な知識をご説明します。
離婚したいと思ったときの初期対応
まずは落ち着いて現状を整理する
離婚を考えたときは感情的になっていることも多く、すぐにでも離婚の話し合いや手続きを進めたいと思うこともあるでしょう。
しかし、別居や離婚により生活に大きな変化・影響がありますので、準備が必要です。準備のため、まずは現状を整理することが大切です。
〈問題点を確認する〉
離婚するかどうか迷っている場合は、離婚を考えた理由・夫婦の問題点について確認しましょう。原因や問題点を具体的に考えることで、どのように対応すべきかが見えてきます。
問題点が具体的になったら、その問題が、夫婦での話し合いや第三者に相談すること等で、解決・改善できるのか、それとも解決・改善できないかを考えます。
〈証拠・情報の収集〉
離婚にあたって、財産分与、養育費、親権、慰謝料など様々なことを話し合って決める必要があります。
財産分与や慰謝料請求などに必要な証拠や資料は集めましたか。
別居後や離婚後に安定した生活を送るためにも、自分が望む条件で離婚するためにも、準備が重要です。
夫婦といえども、相手がどのような財産を持っているか知らないことも多いでしょう。適正な財産分与を実現するためには、相手の財産に関する情報、資料を集める必要があります。
また、たとえば、DVやモラハラを受けているので離婚したい、慰謝料を請求したいと考えている場合、DVやモラハラの証拠を集める必要があります。
離婚を切り出した後や別居後は、資料・証拠を集めることは難しくなりますので、離婚を切り出す前に、別居前に、集めておくことが重要です。
離婚手続きを進める準備ができているか、まずは落ち着いて現状を整理しましょう。
離婚を決意する前に考えておくべきこと
〈離婚のメリット・デメリットを比較する〉
離婚にはメリットだけでなく、デメリットもあります。離婚後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、メリットとデメリットを理解して離婚するか判断することが大切です。
・メリット
① 精神的に解放される
相手への不満や相手と生活することで生じるストレスから解放され、心が落ち着くというメリットが挙げられます。特に、モラハラやDVを受けていた場合、安心して生活できることは大きなメリットです。
精神的安定が得られることで、意欲が湧き、活動的になって、生活を楽しめるようになることでしょう。
② 自分で選択できる
自分の時間を自由に使えるようになり、趣味や仕事に集中できるようになります。
経済的に自立し、自分の判断で人生設計できるようになります。
③ 新しい人生が始まる
新しい人間関係を築きやすくなり、新しいパートナーを見つけたり、再婚ができるようになります。
自分の価値観にあった生活を送ることができ、自分らしく生きることができます。
・デメリット
① 経済的な負担
収入が減る可能性があり、生活水準が下がることもあります。
結婚後に仕事をやめて専業主婦・主夫の期間が長かった場合、離婚後に子育てをしながら仕事をする場合など、十分な収入を得ることが難しく、生活水準が下がることがあり、不安を感じることもあるでしょう。
離婚時の財産分与や養育費がどれくらいもらえるのかなど、事前に見通しを立てることが大切です。
児童扶養手当や医療費の助成など行政による支援を受けられるか確認しましょう。
② 子どもへの影響
生活環境の変化により、子どもに負担が生じることがあります。 子どもが精神的な負担を感じることもあります。父親又は母親と離れて暮らすことになって、子どもが寂しい思いをすることもあるでしょう。
ただ、子どもは新しい環境に慣れて成長していくたくましさももっています。
離婚による子どもへの影響を小さくするために、子どもと別居親との関係を保つようにすることが大切です。離婚後も、子どもにとって大切な父であり、大切な母であることは変わりません。子どもとの面会交流を続け、子どもが寂しい思いをしないですむようにすることは大切です。
③ 生活環境の変化・社会的な変化
新しい生活環境に適用する必要があります。環境の変化により、孤独を感じることもあるでしょう。
〈子どもの親権について考える〉
離婚して夫婦ではなくなっても、子どもの父や母であることに変わりありません。
親は子どもを守らなければなりません。
未成年の子どもがいる場合、誰が子どもを育てるのか、親権者を決める必要があります。
親権者について、親の感情や都合を優先して結論を出すのではなく、子どもの成長、幸せを第一に考えて決めることが大切です。
親権者になりたいかを考えます。親権者になりたい場合は子どもと離れないようにすることが大切です。親権者を決めるときに重要な判断要素になるのが、監護養育の状況、どちらが主に監護養育しているかです。子どもと一緒に生活して育てている親が親権者として適切であると判断される可能性があるということです。
なお、子どもの前で離婚をめぐって言い争いになると、子どもは不安になります。離婚の話し合いは、子どもがいない時間、場所でする配慮が必要です。
〈離婚後の生活設計を立てる〉
別居後や離婚後に安定した生活を送るために、別居後、離婚後の生活を具体的にイメージすることが大切です。
別居後・離婚後の生活、特に住居や生活費の目処は立っていますか。生活するのにいくらかかるのか確認し、どのくらい収入が必要か計算しましょう。 お金の準備も必要不可欠です。
離婚後の生活について、経済的に生活していけるか見通しを立てることが大切です。お金の見通しが立たない場合は、別居や離婚のタイミングを検討する必要があります。離婚後の収入・支出について慎重に検討したうえで、別居・離婚のスケジュールを立てることが大切です。
離婚を切り出す前に、財産分与や慰謝料などでどのくらい得られるのか見通しを立てることも大切です。離婚を切り出した後は、相手の通帳など相手の財産を確認することが難しくなります。離婚を考え始めた時点で、相手の持っている財産を把握するようにしましょう。財産に関する重要な資料はコピーや写真を撮るなどしておくことをおすすめします。
財産分与や慰謝料を得ることができたとしても、それだけで十分なお金を得られることは一般的にはあまりありません。離婚後に安定した生活を送るには収入の確保が大切です。
特に、長い間、専業主婦・主夫をしてきた方は、生活費を確保するために仕事を見つける必要があります。安定した生活を送るには、別居や離婚する前に仕事を探しておくのが望ましいです。離婚を考え始めた時点で、パート・アルバイトを始めるなどして準備を進めるのがよいでしょう。
離婚後の住居についても考える必要があります。離婚後は、夫婦のどちらか一方、または両方が新しい住まいで生活することになります。実家に頼ることができる場合には、実家に転居することも1つの方法です。
子どもがいる場合、子どもの生活への影響も考える必要があります。子どもがいる場合は、子どもの将来についても考えて、離婚後の生活・子育てに向けた環境づくりを始めておくことが必要です。離婚に際して、養育費について取り決めておくことが必要です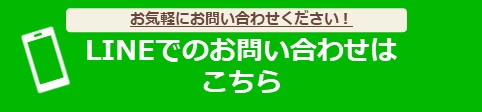
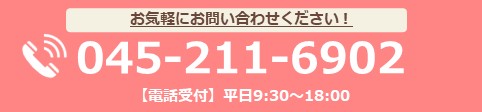
離婚の種類
離婚を成立させる手続きとして、協議、調停、審判、裁判があります。
協議離婚
協議離婚は、裁判所を通さず、夫婦での話し合いによって離婚することです。夫婦双方が離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出することで離婚が成立します。
夫婦が合意すれば、法律で定める離婚事由がなくても離婚できます。
〈協議離婚のメリット〉
裁判所を通さないので時間がかからない
離婚条件を自由に決められ、柔軟な解決が可能である
負担が少ないなど
〈協議離婚のデメリット〉
相手と直接話し合うことによる精神的負担・ストレスがある
感情的になって話し合いが進まないことがある
相手が応じないと離婚が成立しないなど
協議離婚のデメリットを補う方法として、相手との協議を弁護士に依頼することが考えられます。相手との交渉を弁護士に任せることで、精神的ストレスを軽減できますし、離婚後の生活準備に時間を使うことができるようになります。
調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所での調停という手続きで成立する離婚です。
離婚調停は、夫婦での話し合いが難しい場合に、家庭裁判所で、調停委員を介して離婚について話し合う手続きです。調停委員が間に入って夫婦双方から話を聞き、調整しますので、相手と顔を合わせずに話し合いを進めることができます。
調停離婚の場合も、協議離婚と同様に、法律が定める離婚事由がなくても離婚することができます。離婚の成立には夫婦の合意が必要となり、どちらかが離婚に応じない場合は離婚が成立しない点も協議離婚と同じです。
〈調停離婚のメリット〉
相手と直接顔を合わせることなく話し合いができる
柔軟な解決の可能性がある
プライバシーが守られる(調停は非公開の手続きです。)など
〈調停離婚のデメリット〉
時間がかかる
負担が生じる
相手が応じないと離婚が成立しないなど
離婚調停で有利に話し合いを進めるには、説得的な主張をすることが大切です。主張を裏付ける証拠があれば有利に話し合いを進めることができるでしょう。
審判離婚
審判離婚は、家庭裁判所の調停に代わる審判で成立する離婚です。
家庭裁判所は、離婚調停が成立しない場合において相当と認めるときは、職権で、事件の解決のために必要な審判(調停に代わる審判)をすることができます。
調停に代わる審判に対して、審判を告げられた日から2週間以内であれば異議を申し立てることができます。異議の申立てがあれば、審判は効力を失います。そのため、夫婦のどちらかが離婚を明確に拒否しているなど、審判に対して異議の申立てがなされることが確実に予想される場合には、家庭裁判所が審判をする意義が乏しく、審判が行われるケースは多くありません。通常は、離婚調停が不成立となった場合、離婚裁判を検討します。
次のようなケースでは、審判によって離婚が成立することがあります。
① 離婚条件の大部分について合意しているが、養育費の額など一部の離婚条件について少しの差で合意に至らない場合
親権や財産分与などの離婚条件について、双方の考えが大きく異なっている場合は、異議が出される可能性が高く、審判するのに適したケースとはいえません。
② 当事者が調停に参加できない事情のある場合
離婚条件については合意できているが、当事者の一方が病気などによって調停に参加できない場合に審判が出されることがあります。
〈審判離婚のメリット〉
・審判は非公開の手続きであり、プライバシーが守られる。
なお、裁判は原則として公開の法廷で行われます。
・柔軟な解決が可能
家庭裁判所は、双方の衡平を考慮して、調停に表れた一切の事情を考慮して審判を行います。当事者の立場からすると、調停に代わる審判には、家庭裁判所から、夫婦の実情をふまえた柔軟な解決案を示してもらえるというメリットがあるといえます。
・裁判に進む場合よりも、時間や費用の面での負担が軽く済む。
裁判になると、双方が主張や証拠を提出して裁判が進みますが、通常、その準備を含めた時間、労力、費用がかかります。審判の場合には、これらの負担を軽減できるというメリットがあります。
・強制執行できる。
審判書の送達を受けた日から2週間以内にいずれからも異議申立てがない場合、審判が確定し、判決と同じ法的効力をもちます。そのため、たとえば、養育費の支払いについて審判が出ていれば、その審判に基づいて、相手の財産(預金、給与など)を差し押さえる手続を裁判所に申し立てることができます。
〈審判離婚のデメリット〉
・異議申立てがなされると、審判の効力が失われる。
裁判所から送達された審判書を受け取った日から2週間以内に異議の申立てがあれば、審判は効力を失います。
裁判離婚
裁判離婚は、裁判官が言い渡す判決によって成立する離婚です。
離婚について、いきなり裁判(訴訟)をすることはできず、まず調停を行う必要があります(調停前置主義)。家庭内の問題は、裁判よりも話し合いで解決することが望ましいと考えられているからです。
裁判(判決)で離婚が認められるには、法律で定められている離婚事由があることが必要です。法律上の離婚事由があれば、一方が離婚に反対していても裁判官が離婚を認める判決を言い渡すと離婚が成立します。なお、裁判の途中で、話し合い(和解)により離婚を成立させることもできます。
〈裁判離婚のメリット〉
相手が離婚に応じなくても離婚事由がある場合には離婚が成立する
〈裁判離婚のデメリット〉
時間がかかる
負担が生じる
プライバシーが守られない(裁判は原則として公開です)など
裁判では、主張と証拠を提出することになります。有利な内容の判決を得るためには、法律知識等が必要です。
裁判では、判決という形で結論が出ますが、自分に不利な内容の判決となることもありますので、裁判になる前から裁判になった場合の見通しをたて、離婚手続きを進めることが大切です。
判決に対して不服申立て(控訴等)があると、さらに裁判が続きます。
裁判まで行うとなると、時間や費用など負担が大きくなります。
離婚は大きな決断ですので、ある程度の負担は避けられませんが、必要以上に時間や費用を費やすことがないよう、離婚を考え始めたら、早い段階で弁護士に相談するのがよいでしょう。
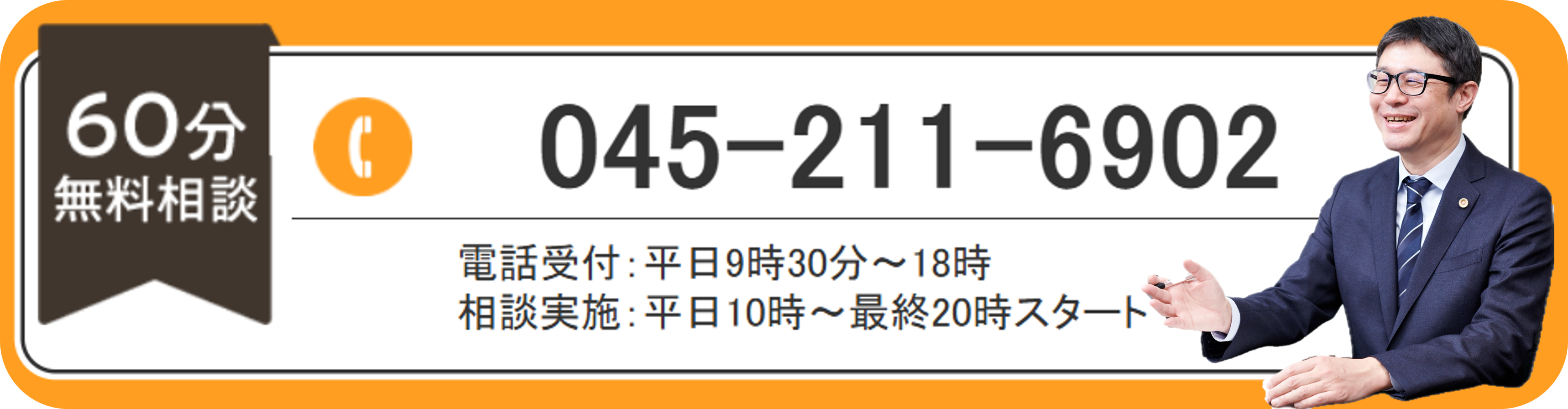
離婚に必要な手続きと書類
必要書類
〈協議離婚の場合〉
① 離婚届
市区町村役場で入手することができます。自治体によってはホームページからダウンロードすることもできますが、A3サイズで印刷するなど注意事項がありますので、確実に受理してもらえるよう、提出する予定の市区町村役場に確認することをおすすめします。また、書き直しに備えて、複数枚準備しておくのがよいでしょう。
協議離婚では、離婚届を提出することで離婚が成立します。
② 届出人の本人確認書類
・運転免許証
・パスポート
・マイナンバーカードなど
本人確認書類について、市区町村役場に事前に確認しましょう。
〈調停離婚、裁判離婚、審判離婚などの場合〉
① 離婚届
市区町村役場で入手することができます。自治体によってはホームページからダウンロードすることもできますが、A3サイズで印刷するなど注意事項がありますので、確実に受理してもらえるよう、提出する予定の役所に確認することをおすすめします。また、書き直しに備えて、複数枚準備しておきましょう
調停離婚では調停が成立した日に、審判離婚では審判が確定した日に、裁判離婚では裁判が確定した日に、それぞれ離婚が成立しますが、離婚届を提出する必要があります。
離婚届は、調停の成立日、審判・判決の確定の日から10日以内に提出しなければなりません。
② 添付書類
調停離婚の場合:調停調書の謄本
審判離婚の場合:審判書の謄本と確定証明書
裁判離婚の場合:判決書の謄本と確定証明書
和解離婚の場合:和解調書の謄本
認諾離婚の場合:認諾調書の謄本
離婚届の書き方
〈離婚届作成前の注意点〉
離婚届を書く前に次の点に注意しましょう。
① 離婚条件を検討する
自分が望む離婚条件を実現するには、離婚届を提出する前に、離婚条件について話し合い、合意すること、合意した内容を書面に残すことが重要です。
養育費の請求は離婚後でもできますし、年金分割については離婚から2年以内であれば請求できます。また、財産分与についても離婚から2年以内であれば請求できます。
しかし、離婚成立後は、相手が話し合いに応じてくれない可能性もありますし、話し合いに応じてくれても不利な内容となる可能性もあります。離婚後の生活を安定させるためにも、離婚届を提出する前に離婚条件について話し合い、合意することが大切です。
また、離婚届に署名して提出すると、通常、後から離婚条件を変更することはできません。
たとえば、親権者を取り決めると、後から親権者を変更することは多くの場合難しいでしょう。
離婚届の作成・提出は、離婚条件について合意し、合意内容を記載した書面を作成した後にすることが重要です。
② 離婚協議書・公正証書を作成する
離婚条件について合意できれば、その合意した内容を記載した書面を作成しましょう。
口約束では、後になって、そんな約束はしていないと言われるなど、トラブルになるおそれがあります。
費用はかかりますが、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておくと、養育費や慰謝料等の支払いがなされない場合、裁判を行うことなく、相手の給与や預金などの財産を差し押さえる手続を裁判所に申し立てることができます。
③ 弁護士に相談する
適切な離婚条件について自分で判断することは簡単ではありません。
法的に適正な離婚条件を確認しないまま話し合いを行うと、不利な条件で合意してしまうことがありますし、法的には困難な離婚条件を求め続けた場合、必要以上の時間や費用がかかってしまうこともあります。まずは、法的な観点から、適正な内容を確認することが大切です。
また、法的に有効な書面を作成するには法律知識等が必要となります。
離婚届を作成する前に、弁護士に相談することをおすすめします。
〈協議離婚の場合の離婚届の書き方〉
離婚条件について話し合いがまとまり、合意書を作成したら、離婚届を作成します。
離婚届には、以下の項目を正確に記載する必要があります。
① 氏名・住所・本籍
氏名・住所は住民票に記載されているとおりに、本籍は戸籍に記載されているとおりに、それぞれ記載します。
② 離婚の種別
協議離婚の横にある□にしるしをつけます。
③ 婚姻前の氏にもどる者の本籍
結婚前の旧姓に戻る場合に記入します。
結婚して氏(名字)が変わった人は、離婚後の氏について、婚姻中の氏を使い続けるか、結婚前の氏を名のるか、選択することができます。
婚姻中の氏を使い続ける場合は、記入する必要はありません。この場合、離婚の日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
なお、結婚した際には夫婦の戸籍が作成されていますが、その戸籍において筆頭者でない人は、離婚後、次のいずれかの戸籍に入ることになります。
・結婚前の氏を名のり、結婚前の戸籍に戻る
・結婚前の氏を名のり、新しい自分の戸籍を作る
・婚姻中の氏を名のり、新しい自分の戸籍を作る
④ 未成年の子の氏名
親権を取得する側の欄に記入します。
⑤ 届出人署名
協議離婚の場合、夫婦双方の署名が必要です。それぞれ自分で署名します。この欄には、婚姻中の氏を記載します。押印は任意です。
⑥ 証人
協議離婚の場合、離婚届には、成人の方2人の署名が必要です。押印は任意です。
⑦ 面会交流や養育費の取り決め
未成年の子がいる場合、面会交流などの子の監護に必要な事項についての取り決め状況を記載します。
経済的に自立していない子(未成年の子に限られません)がいる場合、養育費の分担についての取り決め状況を記載します。
〈調停離婚、裁判離婚の場合の離婚届の書き方〉
① 氏名・住所・本籍
氏名・住所は住民票に記載されているとおりに、本籍は戸籍に記載されているとおりに、それぞれ記載します。
② 離婚の種別
・調停:調停離婚の場合に、しるしを付け、調停成立日を記載します。
・判決:裁判離婚の場合に、しるしを付け、判決が確定した日を記載します。判決の確定した日については、離婚届と一緒に提出する確定証明書(裁判所に申請して入手します。)で確認しましょう。
・審判:審判離婚の場合に、しるしを付け、審判が確定した日を記載します。審判が確定した日については、離婚届と一緒に提出する確定証明書(裁判所に申請して入手します。)で確認しましょう。
・和解:離婚裁判において和解した場合に、しるしを付け、和解成立日を記載します。
・請求の認諾:離婚裁判において、原告が求めた離婚を被告が認めた場合に、しるしを付け、認めた日付を記載します。
③ 婚姻前の氏にもどる者の本籍
結婚前の旧姓に戻る場合に記入します。
結婚して氏(名字)が変わった人は、離婚の氏について、婚姻中の氏を使い続けるか、結婚前の氏を名のるか、選択することができます。
婚姻中の氏を使い続ける場合は、記入する必要はありません。この場合、離婚の日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
なお、結婚した際には夫婦の戸籍が作成されていますが、その戸籍において筆頭者でない人は、離婚後、次のいずれかの戸籍に入ることになります。
・結婚前の氏を名のり、結婚前の戸籍に戻る
・結婚前の氏を名のり、新しい自分の戸籍を作る
・婚姻中の氏を名のり、新しい自分の戸籍を作る
④ 未成年の子の氏名
親権を取得する側の欄に記入します。
⑤ 届出人署名
調停離婚や裁判離婚の場合、夫婦の一方の署名で足ります。原則として、申立人です。本人が署名します。この欄には、婚姻中の氏を記載します。押印は任意です。
⑥ 証人
協議離婚以外の場合、証人は必要ありません。
⑦ 面会交流や養育費の取り決め
未成年の子がいる場合、面会交流などの子の監護に必要な事項についての取り決め状況を記載します。
経済的に自立していない子(未成年の子に限られません)がいる場合、養育費の分担についての取り決め状況を記載します。
※ 調停成立日や裁判の確定日などから10日以内に離婚届を提出する必要があります。
離婚あたって決めるべきこと
親権
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を決める必要があります。
令和6年に改正された民法では、この改正民法の施行後は、共同親権とすることもできるようになります。必ず共同親権になるわけではありません。この改正民法は、令和8年5月24日までに施行されることになっています。
養育費
養育費とは、子どもが生活するために必要な費用(衣食住の費用や教育費、医療費、娯楽費など)のことです。
子どもが安定した生活を送り、健やかに成長するには養育費が継続的に支払われることが大切です。
両親が離婚した後も、別居している親から養育費が継続して支払われていることを子どもが知ったとき、子どもは別居親の愛情を感じることができます。別居親からの愛情も感じられることは、子どもの成長にとってとても重要なことです。
子どもが自立するまで子どもにかかる費用を負担することは親の義務です。
期間としては、20歳まで、18歳まで、22歳までなど、事情・状況に応じて様々です。
養育費の額は、支払う側と受け取る側の経済力によって異なります。基本的に双方の収入を基準にして算定します。裁判所が養育費算定表を公開しています。算定表は標準的な額を簡易迅速に算定するためのもので、個別事情をすべて考慮して作成されているわけではありません。個別の事情を考慮して算定するのが適切なケースもあります。事案ごとに検討が必要です。
面会交流
面会交流は、未成年の子どもと別居親が、子供に会うことやその他の方法で交流することです。
子どもと会うこと以外にも、電話やメール・LINEなどでやりとりする、学校行事に参加する、写真やプレゼントを送ることなども面会交流です。
会う頻度、時間、場所などは、子どもの年齢、生活等を考えて,子どもに負担をかけることのないように十分配慮し、子どもの意思も尊重して決めることが大切です。
なお、離婚が成立する前の別居期間中でも、家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
財産分与
財産分与(清算的財産分与)は、離婚にあたって、夫婦が結婚後に協力して築いた財産を分けることです。
財産分与のポイントは、簡潔に言えば、「どの財産を」「どう分けるか」です。
〈「どの財産を」:財産分与の対象財産について〉
清算的財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産です。
離婚前に別居している場合、通常、別居後は経済的な協力関係がなくなっていることから、別居時の財産が財産分与の対象となります。
結婚する前から持っていた財産は、財産分与の対象にはなりません。
親等からの贈与・相続により取得した財産は、夫婦の協力により築いた財産ではありませんので、財産分与の対象とはなりません。
夫婦といえども、相手が持っている財産をすべて把握しているとは限りません。
離婚を切り出した後は、相手が持っている財産を確認することが難しくなります。また、離婚前に別居する場合は、別居後は相手方の財産を調べることが難しくなります。
離婚を切り出す前、別居前に、相手が保有している財産を確認しておくことが大切です。
離婚を考えた時点で、相手の財産を確認し、把握するようにしましょう。
〈「どう分けるか」:分け方〉
分け方として、基本的に、財産形成に対する貢献度・寄与度に応じて分けるのが公平であると考えられています。
夫婦には様々な形がありますが、夫婦でそれぞれ役割を分担し、その結果、財産ができます。
基本的に、財産形成に対する貢献度は、50:50とされることが多いです(「2分の1ルール」と呼ばれることがあります)。
財産分与は、半分ずつと法律で決められているわけではありませんので、話し合いで自由に分けることもできます。
財産の額について評価が必要な場合もあります。
たとえば、夫婦の共有財産の中に不動産がある場合で、一方または双方が不動産に住み続けることを希望した場合など、不動産の価値を評価することが必要になりますし、分け方についても話し合う必要があります。
適正な財産分与をするには、事前の準備、法律知識、交渉力が必要になります。
慰謝料
離婚の際の慰謝料については、夫から妻に支払うものというイメージがあるかもしれません。
しかし、夫が不倫や暴力などの有責行為をしておらず、性格の不一致や価値観の違いで離婚することになった場合、夫は慰謝料を支払う必要はありません。妻が夫にDVをしており、妻のDVが原因で離婚することになった場合、夫は妻に慰謝料を請求することができます。
このように、慰謝料を請求できるのは、相手の有責行為により精神的苦痛などの損害を被った被害者です。
慰謝料を請求するには、証拠を確保することが重要です。
たとえば、配偶者が不倫をしていた場合でも、配偶者が不倫していないなど言い張った場合、証拠がなければ慰謝料を支払ってもらうことは困難です。
離婚を切り出す前や別居前に証拠を集めておくことが重要です。
弁護士に相談・依頼するメリット
有利な離婚を実現できる
離婚にあたって検討すべきことは少なくありません。財産分与、慰謝料、親権、養育費、年金分割など離婚条件の話し合いが必要です。別居後や離婚後の住居、別居のタイミングなども考える必要があります。
また、仕事、家事、育児など、日々生活するうえでも考えること、やるべきことはたくさんあります。離婚条件は、忙しい日々の中で検討することになります。
弁護士に相談することで、事情・状況を整理しながら、適切な離婚条件について検討することができます。
法的に適切な条件・内容を知らずに話し合いを行うと、不利な内容で合意してしまうことがありますし、また、解決までに必要以上に時間や費用を使ってしまうこともあります。
自分が望む条件、適切な条件で離婚をするには、なるべく早い時期に弁護士に相談するのが良いでしょう。
相手との話し合いを任せることができる
離婚の話し合い、離婚条件の交渉には精神的な負担・ストレスがかかります。
ラハラを受けていた方など、相手との関係や性格などによっては、自分の言いたいことを言えなかったり、上手く交渉できない方もおられると思います。
夫婦だけの話し合いでは、感情的になってしまい、話し合いが進まないこともあるでしょう。仕事、家事、育児で疲れた状態で話し合いをすることにストレスを感じる方もいるでしょう。
弁護士に交渉を任せることで、交渉によるストレスを軽減することができますし、自分の時間を確保することもできます。
弁護士に相手との交渉を任せることで、自分の時間が確保でき、仕事・家事・育児に時間を使うことができるようになりますし、自分のペースで考える時間ができます。また、別居後や離婚後の生活の準備をする時間ができて、精神の安定にもつながります。
相手や相手の弁護士のペースに巻き込まれずに交渉できる
自分が望む離婚条件での離婚を実現するには、相手との交渉を上手に行うことが必要です。
手続を有利に進めるには、相手や調停委員、裁判官に対して説得的な主張をすることが必要となりますので、資料や証拠が重要です。
準備不足の状態で交渉すると相手のペースで話し合いが進むおそれがあります。相手に弁護士が付いている場合には不利な結果になる可能性が高まります。
弁護士に相談・依頼することで、サポートを受けながら準備を進めることができ、相手のペースにのまれずに交渉を進めることができますので、希望する条件、適正な条件での離婚につながります。
離婚に必要な手続きを任せることができる
話し合いで離婚の条件がまとまる場合も、合意した内容について法的に有効な書面を作成しておくことが大切です。
相手が約束通りに支払わないこともあり得ます。相手がそんな約束はしていないと後々態度を変えた場合、言った言わないの水掛け論になり、話し合って決めたことについて、もう一度話し合うことになりかねませんし、不利な内容になることもあり得ます。事後的なトラブルを防止するために、合意した内容について書面を作成することはとても大切です。
調停や裁判になった場合、事実等を適切に主張し、その裏付けとなる証拠・資料を提出することが重要です。調停が成立した後に、こうしておけば良かったと思っても、不服を申し立てることはできませんので、調停を成立させる前に、調停で合意する内容(調停条項)を慎重に検討する必要があります。
離婚裁判では、判決により決着がつきますが、自分の希望した内容とは異なる結論が出された場合も判決に従う必要があります。不利な判決とならないよう、適切に主張し、証拠を提出することが重要です。
合意書等の書面が作成されていても、約束した内容を相手が履行しないこともありますので、裁判所を通じて、相手の給与を差し押さえるなどの強制執行をすることもあります。
離婚後に安定した生活を送るには、協議、調停、裁判、強制執行のどの段階においても専門家のアドバイス・サポートが有益です。弁護士は、離婚協議、調停、裁判、強制執行まですべての手続きをサポートすることができます。
まとめ
準備が結果を左右することは少なくありませんが、離婚においても準備が重要です。
離婚を考えたときは、早く離婚したいという気持ちになっていることもあるでしょう。
しかし、離婚後は生活面でも精神面でも大きな変化・影響が生じますので、準備が不可欠です。
離婚を考えたときは、まず、現状を整理し、自分の気持ちを確認し、離婚後の生活の見通しを立てることが大切です。
離婚の決意が固まったときは、話し合うべき離婚条件について検討することになりますが、適正な離婚条件で離婚するには、情報収集と資料・証拠収集が大切です。
離婚の準備は、仕事・家事・育児といった日々の生活を送る中で進めることになりますので、時間の面でも、精神面でも負担がかかります。
また、離婚後、合意した内容を守ってもらえない事態が生じることがありますので、将来のトラブル予防についても気を配る必要があります。
一人で準備をすることは負担ですし、一人で準備することが難しい方もおられるでしょう。
離婚後に安定した生活を送るために、一人で悩まず、弁護士に相談することをおすすめします。


