離婚後の生活費について心配な方は多いのではないでしょうか。
離婚後のお金の問題は避けて通ることができませんし、重要なことです。
離婚条件について、離婚後に、やっぱり納得いかないと思っても、離婚後は、相手が話し合いや条件の変更に応じないケースがほとんどでしょう。
離婚後にお金のことで後悔しないように、離婚する前に、離婚の際のお金・財産について、どのくらい請求できるのか十分に検討したうえで、合意しておくことが必要です。
離婚時に受け取れるお金・財産
離婚時にお金・財産を請求する方法・制度として、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割があります。
財産分与とは
財産分与は、離婚にあたって、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分けることです。
夫婦の協力関係終了時の財産が財産分与の対象となります。離婚前に別居が先行しているケースでは、通常、別居時の財産が財産分与の対象となります。
慰謝料
慰謝料は、相手方の有責行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求できる賠償金のことです。
離婚の際に必ず支払われるものではなく、どんな場合でも請求できるわけではありません。
浮気・不倫や暴力などの不法行為・有責行為がある場合に請求できます。
単なる性格の不一致が原因で離婚する場合など、相手に重大な落ち度や責任がない場合は慰謝料を請求することはできません。
また、慰謝料は、夫から妻に支払われるものでもありません。妻が離婚の原因を作ったのであれば、夫は妻に慰謝料を請求できます。
養育費
養育費は、子どもと一緒に住んでいない親(別居親)が、子どもと同居して養育している親(監護親)に支払う子どもの生活費です。
養育費には、子どもが生活するために必要な衣食住の費用、教育費、医療費、娯楽費などが含まれます。
年金分割
年金分割は、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績を多い方から少ない方に分割する制度です。
年金分割の結果、それぞれが受け取る年金額が変わります。年金分割は、婚姻期間中に納付した保険料を分割するものですので、相手が死亡した後も、年金を受け取ることができます。
財産分与の交渉を有利に進めるポイント
財産分与には、3つの要素があると考えられています。
①夫婦が共同生活を送る中で築いた財産の公平な分配(清算的財産分与)
②離婚後の生活保障(扶養的財産分与)
③離婚の原因を作ったことへの損害賠償(慰謝料的財産分与)
①清算的財産分与が基本であると考えられています。③慰謝料的要素は財産分与ではなく、別途、離婚慰謝料で話し合われることが多いです。②扶養的財産分与は、清算的財産分与や離婚慰謝料では離婚後の生活維持が難しい場合に補充的に認められています。
ここでは、主に清算的財産分与について説明します。
財産分与について話し合う際には、次のポイントを押さえておきましょう。
財産分与の対象となる財産の把握
〈対象となる財産〉
財産分与の対象となる財産は、「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産」です。
共有名義のものだけでなく、配偶者の名義であっても、ご自身の名義であっても、夫婦で協力して形成・維持してきた財産が財産分与の対象となる財産(共有財産)にあたります。
現金・預金、不動産、自動車、株式、投資信託、保険(生命保険等の解約返戻金)、家財道具などです。
不動産など、その価値を評価することが必要な財産もあります。高額な財産、例えば不動産をいくらと評価するかによって、財産分与の金額は大きく変わりますので、評価額が争いになることはしばしばあります。
夫婦生活に必要な支出等のために負担した債務、たとえば、住宅ローンなどは財産分与において考慮されます。
他方、ギャンブルのためにできた借金など、婚姻生活とは無関係の借金は財産分与において考慮しません。
資産と負債の両方がある場合、資産から負債を差し引いて、プラスとなれば財産分与を請求することができます。
なお、未払いの婚姻費用がある場合、財産分与において考慮することができます。
〈どの時点の財産を分けるのか〉
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻後、離婚するまでに築いた財産です。
もっとも、別居後は、夫婦間に経済的な協力関係がなくなっていると考えられることから、離婚前に別居が先行しているケースでは、通常、別居時の財産が財産分与の対象となります。
〈共有財産の確認〉
財産分与の額を正しく算定するには、まず、財産分与の対象となる共有財産について正確に把握する必要があります。
夫婦とはいえ、配偶者がどのような財産を持っているか分からないこともよくあることです。相手方の財産については、教えてもらっている財産以外にも財産がないか、確認・検討する必要があります。
そのためには、対象となりうる財産をできる限り正確にリストアップし、把握することが必要です。
将来受け取る退職金などを忘れていませんか。銀行、証券会社、保険会社などから郵便物が届いているか確認することも大切です。郵便が届いている銀行等に財産がある可能性があります。
財産のリストアップや把握は、弁護士に相談しながら進めるのがよいでしょう。
〈離婚を切り出す前、別居する前に、財産を確認しましょう〉
離婚の話をすると、配偶者が財産を隠す可能性があります。離婚を切り出す前に、相手の持っている財産を確認しておくことが重要です。
また、別居後に相手の財産を調査することには限界がありますので、別居前に、相手の財産について確認しておきましょう。
特有財産と共有財産の区別
結婚前から持っていた財産(結婚前に貯めた預金など)は財産分与の対象にはなりません。
親などから贈与された財産、相続した財産も、夫婦の協力により築いた財産とはいえませんので、財産分与の対象になりません。
このような財産を「特有財産」といいます。
離婚時点で、夫または妻の名義の預金があった場合、この預金が特有財産か夫婦共有財産か問題となることがあります。結婚する前に貯めていた特有財産である預貯金に、婚姻後に形成したお金が混ざっている場合もあるでしょう。通帳の記載などから、共有財産ではなく特有財産であることを説明し、証明することが重要となります。
婚姻期間と財産形成への貢献度
財産分与の割合は基本的には2分の1です。「2分の1ルール」と呼ばれることがあります。
貢献度・寄与度に応じて財産を分けるのが公平だと考えられています。貢献度・寄与度が明確でなければ同等と推定されます。
夫婦の一方が財産形成に大きく貢献していた場合には、割合が修正されることもあります。夫婦の一方の特別な資格や能力によって多額の財産が築かれた場合は、分与の割合が修正されることもあります。生活費は2分の1ずつ負担していたにもかかわらず、配偶者はギャンブルや浪費で預貯金がゼロ、夫婦の共有財産といえるのは、自分が長年コツコツ貯めてきた預貯金だけというケースでは、財産形成に対する自分の貢献度が大きいとして、コツコツ貯めた自分の貢献度を2分の1よりも多く認めるという結論はあり得ます。
―――民法改正―――
2024年5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この改正民法は2026年5月までに施行予定です。
改正後の民法768条3項には、「婚姻中の財産の取得又は維持についての買う当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」と定められています。
もっとも、法律では、絶対に2分の1でなければならないと定めているわけではありません。寄与(貢献)の程度が異なるときはその割合で分与することを否定していません。
この改正では、財産分与を行う際に考慮すべき事情が定められました(改正民法768条3項)。財産分与を判断する際の考慮事情として、次のものが挙げられています。
① 当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額
② その取得又は維持についての各当事者の寄与の程度
③ 婚姻の期間
④ 婚姻中の生活水準
⑤ 婚姻中の協力及び扶助の状況
⑥ 各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入
⑦ その他の一切の事情
扶養的財産分与
財産分与には、3つの要素があると考えられています。
①夫婦共有財産を分け合う「清算的財産分与」、②離婚後の扶養のための「扶養的財産分与」、それと③「慰謝料的財産分与」です。
裁判所の実務では、財産分与については、まず清算的財産分与を検討し、清算的財産分与や離婚に伴う慰謝料などでは不十分な場合に扶養的要素が検討される傾向があるようです。
妻が結婚を機に退職し、長年にわたり家事・育児をして家庭を支えたという夫婦は少なくありません。離婚後は、婚姻費用(生活費)を請求することはできませんので、仕事を辞めた妻は、離婚後は自分で生活していかなければいけません。しかし、離婚後、妻がすぐに経済的に安定した生活をするだけの収入が得られる就職先を見つけることができないことも多いと思われます。
その一方で、夫は、離婚後も引き続き仕事を続ければ、これまでと同様の生活を送ることもできますが、夫が仕事を続けて稼げるようになったのは、自らの努力や才能だけではなく、妻が家事・育児をして夫が働ける環境を整えてきたからでもあります。
そうであれば、離婚後であっても、仕事をしている夫が妻をある程度扶養することが公平であるという考え方が扶養的財産分与です。
改正民法768条3項にある⑤婚姻中の協力及び扶助の状況、⑥各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入などは扶養的財産分与に関係する事情と考えられます。
離婚協議書の作成の重要性
話し合いがまとまったら、その内容を書面に残しておきましょう。
口約束だけでは、後々、「そんな約束はしていない」などと支払を拒否されるおそれがありますので、合意した内容を書面に残しておくことが大切です。
離婚協議書は自分で作成することもできますが、形式に不備があったり、内容が不明確であったりすると、証拠としての効力がないという事態も起こり得ます。
離婚協議書の作成に不安があれば弁護士に作成を依頼すると良いでしょう。
また、書面を作成した場合であっても、相手方が約束したとおりに支払ってくれるとは限りません。支払が滞った場合に備えて、公証役場で公正証書を作成するのが良いでしょう。相手方がお金を支払わなかった時に給料や預貯金などを差し押さえる強制執行をする効力を付与した公正証書(強制執行認諾文言が記載された公正証書)を作成しておけば、裁判を経ずに強制執行を裁判所に申し立てることが可能となります。
慰謝料の交渉を有利に進めるポイント
慰謝料が発生する根拠・原因
慰謝料は、相手方の不法行為・有責行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求できる賠償金のことです。
離婚の際に必ず支払われるものではなく、どんな場合でも請求できるわけではありません。単なる性格の不一致が原因で離婚する場合など、相手に重大な落ち度や責任がない場合は慰謝料を請求することはできません。
不貞行為(浮気、不倫)やDV(家庭内暴力)、モラハラなどの不法行為・有責行為がある場合に慰謝料を請求できます。
〈不貞行為〉
不貞行為とは、一般的には、自由な意思に基づいて配偶者以外の人と肉体関係を持つことをいいます。
〈DV(家庭内暴力)〉
ドメスティック・バイオレンス(DV)は、配偶者や交際相手などの親密な関係にある(または、あった)者から振るわれる暴力という意味で使われています。
対象となりうる暴力として次のものが挙げられます。
・身体的なもの(なぐる、ける、髪をひっぱる、首をしめる、腕をねじる、引きずりまわす、物をなげつけるなど)
・精神的なもの(大声でどなる、「誰のおかげで生活できるんだ」などと言う、親族や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする、無視して口をきかない、人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりするなど)
・経済的なもの(生活費を渡さない、働くことを制限するなど)
・性的なもの(性行為を強要するなど)
なお、内閣府男女共同参画局では、対象となりうる暴力の例が挙げられています。
参考:https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/dv/02.html
〈モラルハラスメント〉
モラルハラスメント(モラハラ)とは、言葉や行動、態度で相手に精神的苦痛を与えることをいいます。精神的な嫌がらせです。
次のような発言や態度がモラハラの例として挙げられます。
・人格を否定:「お前は何をやってもダメだ」、「そんなこともできないのか?」
・支配的な発言:「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」
・無視や冷たい態度:「話す価値もない」、「勝手にすれば」、長期間口をきかない
・過度な束縛:「どこに行くか逐一報告しろ」、行動を細かくチェックして自由を奪う
・感情を利用したコントロール:「お前のせいでこんなに辛い思いをしている」と罪悪感を植え付ける
・価値観の押し付け:「普通はこうするべきだろ」、「常識的に考えて○○だろ」
・比較して貶める:「○○さんの方が優秀だ」
証拠の収集と保全
慰謝料を請求する場合、相手方の有責行為を証明する証拠が必要となります。
証拠を集めて、残しておくことが重要です。証拠がなければ、相手方は不法行為・有責行為はなかったと否定する可能性が高く、慰謝料を支払おうとはしないでしょう。裁判でも証拠がなければ、慰謝料請求は認められません。証拠となり得るものとしては、次のものがあります。
・不貞行為の場合:
肉体関係があったとわかる内容のメール、LINE等のSNS
ラブホテルや不倫相手の自宅に出入りしている写真や動画
ラブホテルや旅行先のホテルの領収証など
・DVやモラハラの場合:
DVやモラハラ時の動画・音声
モラハラ発言が書かれたLINE等 ケガの写真
医師の診断書
日常的にDVやモラハラを受けていた事実を記録した日記・メモなど
慰謝料の相場と増額のポイント
〈慰謝料の相場〉
精神的苦痛を金銭的に評価することは難しいですが、裁判例を参考にすると、300万円程度までの範囲にとどまることが多いようです。
慰謝料の額は事情によって異なります。
〈慰謝料増額のポイント〉
増額事由として挙げられるものとして次のものがあります。
・浮気の期間が長い、回数が多いなど悪質であること
・暴力の回数が多い、程度がひどいなど悪質であること
・相手方の問題行動により、大きな怪我を負った、うつ病になったなど
・浮気や暴力を二度としないと約束したのに、約束に違反した
・婚姻期間が長いなど
慰謝料を請求できるのか、どのような証拠が必要なのか、どのような事情が増額事由となるのか、配偶者の問題行動で増額事由になるものはないかなど疑問をお持ちの方は弁護士に相談するのがよいでしょう。
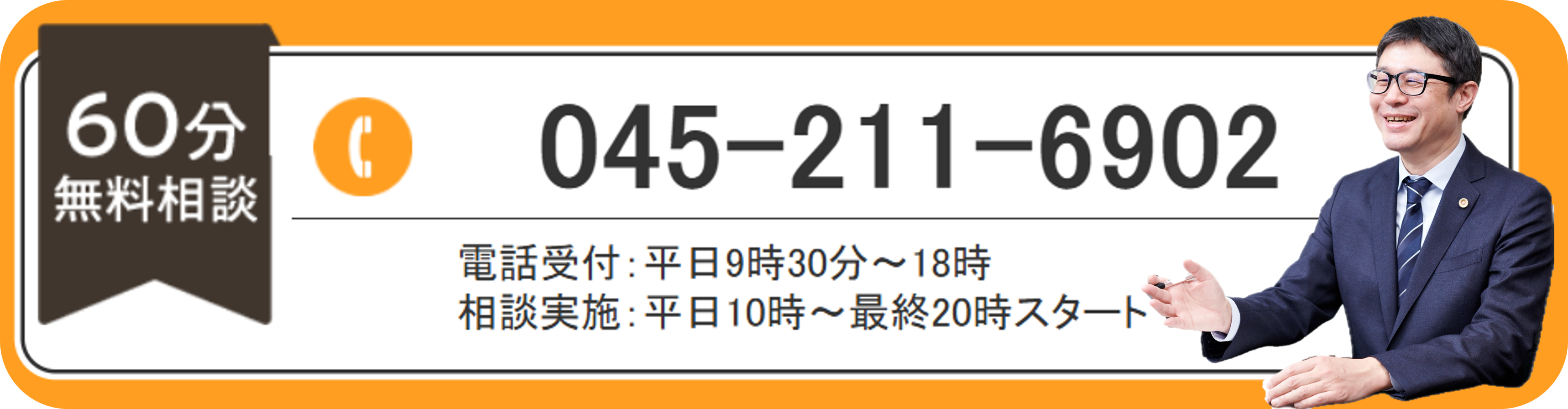
養育費の交渉を有利に進めるポイント
養育費とは
養育費は、子どもが生活するために必要な費用(衣食住の費用や教育費、医療費、娯楽費など)のことです。
子どもと同居していない親(別居親)に対して、養育費を請求することができます。
子どもが自立するまでに必要な費用を負担することは親の義務です。
養育費の算定基準
養育費は、基本的に、父母双方の収入によって算定されます。
裁判所が早見表(養育費算定表)を示しており、調停や裁判になった場合、算定表に基づいて算出されることが多いです。
算定表は、標準的な額を簡易迅速に算定するためのものですので、個別事情をすべて考慮して作成されているわけではありません。
例えば、私立学校に通っている場合など、個別事情を考慮して養育費を算定することが必要なケースもあります。
どのような事情が養育費の額に影響を与えるか検討が必要になりますので、弁護士に相談するのがよいでしょう。
子どもの年齢と養育費の金額
子どもの成長に伴い、子どもの生活費も変化します。算定表は、子どもの年齢が「0~14歳」、「15歳以上」と分けて作成されています。
養育費の額も子どもの成長にそって考える必要があります。
養育費の支払期間と変更
期間の目安としては、20歳まで、18歳まで、大学を卒業する22歳までなど、事情・状況に応じて様々です。
養育費は、通常、支払期間が長期に及びます。
時間が経過する中で、事情が大きく変わることもあります。
たとえば、支払う側が再婚して子どもができた、受け取る側が再婚して再婚相手と子どもが養子縁組した、支払う側や受け取る側が失業した、病気になり療養のため働くことができなくなった等、様々なことが起こり得ます。
そのような事情が生じたとしても、当然に、養育費が減額されることや増額されることはありません。
経済的事情が大きく変化した場合、養育費の額を変更するには話し合いが必要になります。話し合いで合意できない場合は、増額、減額を求めて、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
養育費の取り決めと書面の作成
養育費を取り決めるときは、金額だけでなく、支払の条件を具体的に決めましょう。支払いが止まってしまったときに備えて、法的手続で支払わせることができるよう具体的な条件を決めて、書面に残しておきましょう。できれば、強制執行できるように、公証役場で公正証書を作成しておきましょう。
書面の作成に不安があれば、弁護士に相談することをおすすめします。
年金分割のポイント
年金分割とは
年金分割は、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績を多い方から少ない方に分割する制度です。
公的年金には「国民年金」と「厚生年金」がありますが、分割できるのは厚生年金部分です。
年金分割の結果、それぞれが受け取る年金額が変わります。配偶者より給料が低かった場合や専業主婦の場合、年金分割をすると、年金を受け取るときに加算されるため、年金分割は離婚後の重要な財産といえます。
なお、離婚から2年を経過すると年金分割の請求ができなくなります。年金分割の手続きは、離婚から2年以内にする必要があることに注意しましょう。
合意分割と3号分割
年金分割は、離婚したら自動的に行われるわけではなく、年金分割の手続きを行う必要があります。
年金分割には、合意分割と3号分割があります。
〈3号分割〉
3号分割の方が手続き的には簡単ですが、注意が必要です。
3号分割の対象期間については2分の1の分割がなされます。
もっとも、3号分割で分割されるのは、平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者(会社員や公務員の扶養配偶者。専業主婦、パート等)であった期間中の厚生年金保険料の納付実績だけになります。
〈合意分割〉
合意分割の場合は、婚姻期間中全体の厚生年金保険料の納付実績が分割されます。3号分割とは異なり、平成20年より前の部分も分割の対象期間に含まれます。
合意分割の場合、分割割合は、話し合いによって決めます。
年金は老後の生活保障であることから、家庭裁判所で決めることになった場合、基本的に分割割合は0.5(2分の1)と定められます。
合意分割の手続きの流れ
〈合意分割の場合〉
・情報・資料の入手
合意分割をする場合、分割割合を決めるために、分割の対象となる期間やその期間における双方の情報を正確に把握する必要がありますので、「年金分割のための情報通知書」を年金事務所等で入手します。
年金分割により自分が年金をどのくらいもらえることになるのかを確認することも大切です。50歳以上であれば、見込額の照会を希望すると、分割後の年金見込額を知ることができます。照会の手続きは年金事務所で行うことができます。
・話し合い
「年金分割のための情報通知書」を入手したら、年金分割について話し合います。年金分割することに合意できたら、どのくらいの割合で案分するかを話し合います。なお、年金は老後の生活保障であることから、家庭裁判所で決めることになった場合、基本的に分割割合は0.5(2分の1)と定められます。
・書面の作成
話し合いでまとまったら、その内容を書面として残します。
年金事務所で合意分割の請求手続をする際には、年金分割すること及び分割割合について合意していることを証明する書類が必要ですので、作成に不安があれば弁護士に相談するのが良いでしょう。
・調停の申立て
合意できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停では、基本的に調停委員を介して分割割合について話し合います。合意できなければ調停は不成立となり、審判手続きに移行します。
審判では、裁判所が分割割合を決定しますが、特別の事情がない限り、分割割合を0.5(2分の1)とする審判がされます。
・年金事務所等での請求手続き
年金分割の割合が決まったら、離婚後に年金事務所で年金分割の請求手続きを行います。
合意分割では、基本的には、夫婦2人で手続きに行くことが必要となります。審判や調停で分割割合が決まった場合、当事者のいずれか一方から、年金事務所等において、年金分割の請求手続を行う必要があります。
合意が成立したことにより、また、家庭裁判所の審判や調停に基づいて、自動的に分割されるわけではありませんので年金事務所での手続きを忘れずに行いましょう。
年金分割の請求に必要な書類について、詳しくは年金事務所等で確認できます。
〈3号分割の場合〉
3号分割の手続きは、夫婦2人の合意は必要がなく、第3号被保険者であった方が1人で行うことができます。
交渉における注意点
感情的にならず冷静に交渉する
離婚や離婚条件の話し合いでは、感情的になってしまうことも多いでしょう。
しかし、感情的になって、相手を責めたりすると、相手も態度を硬化させて話し合いがスムーズに進まない可能性があります。
また、感情的になって、離婚条件について安易に合意しないよう注意しましょう。
話し合いを有利に進めるには、感情的にならず、冷静に交渉することが大切です。
調停や裁判になった場合の流れ
話し合いで合意できなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員や裁判官を介して話し合いを行います。調停委員から法律に基づいた説明がなされたり、解決案が示されることがありますので、夫婦だけでの話し合いと比べて、合意の可能性が高まります。
調停でも合意できなかった場合は、裁判を提起することができます。
裁判の途中で、和解により解決することもできますが、和解できなければ、裁判官が判断を下します。裁判官の出した判断(判決)が希望した内容とは異なり、自分に不利な内容であっても、判決に従う必要があります。
弁護士への相談・依頼のメリット
離婚に際しては、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流、年金分割といった離婚条件について話し合うことになります。
適正な離婚条件を検討し、ご自分からも離婚条件について主張する必要があります。また、配偶者と直接交渉することは精神的な負担・ストレスを伴います。
弁護士に相談することで、事情・状況を整理して、適切な離婚条件について検討することができます。弁護士に相談・依頼することにより、法的な観点から検討が可能となり、離婚条件などについて適切に交渉を進めることができますし、交渉による精神的な負担・ストレスを軽減できます。
話し合いで離婚の条件がまとまる場合も、事後的なトラブルを予防するために、合意した内容について法的に効力のある書面(離婚協議書)を作成することが大切です。相手方が約束どおりに支払いをしてくれるとは限りません。法的に有効・適切な内容の書面を作成することにより、事後的なトラブルを予防できる可能性が高まります。
調停や裁判(訴訟)は、裁判所が関与する手続ですが、裁判所が積極的に事実を解明したり、解決のために積極的に活動してくれるわけではありません。
調停では、裁判所の調停委員が、夫婦双方から話を聞いて合意の成立を目指しますが、口頭での説明では正確に伝わらなかったり、誤解を生じることもあります。事実関係や言い分を調停委員に正確に伝えて理解してもらうためには、自己に有利な事実等を整理して適切に主張し、その裏付けとなる資料を提出することが重要です。そのためには、法的な知識を持ち、裁判例などの調査、法的な判断等が必要になります。
裁判では、判決により決着がつきます。自分の希望した内容の結論でなくても、判決に従わなければなりません。裁判を進めていくには法的知識や技術が必要です。
弁護士は、調停や裁判で代理人として活動できますし、裁判となった場合を見すえて活動することができます。
配偶者が経営している会社の財産は、財産分与の対象となりますか?
会社の財産は、会社という法人の財産であって、夫婦の財産ではありません。そのため、原則として、財産分与の対象とはなりません。
もっとも、配偶者が経営している場合は、その会社の株式を持っていることが多いでしょう。その株式に価値があれば財産分与の対象となることがあります。ただ、その株式の価値をどのように評価するか問題になります。特に、上場されていない株式の場合、その評価が問題となります。
なお、夫婦が協力して営んでいる事業が法人化されたが、その法人の実態が家族経営の個人事業と同視できる場合、法人の資産を夫婦の共有財産と評価して財産分与の対象に含めることができるとの考えもあります。
事案ごとの検討が必要ですので、弁護士に相談するのがよいでしょう。
養育費として、大学の学費を請求することはできますか?
(元)配偶者が大学進学を承諾していなかった場合、(元)配偶者に請求できないことがあります。
承諾については、(元)配偶者の明示の承諾がなくても、収入、資産、学歴等から推定的承諾が認められる場合もあります。
(元)配偶者の負担額を決める際には、既に考慮されている公立学校の教育費を控除し、通常、父母の収入で按分して算出します。
子どもの奨学金やアルバイト収入がある場合、これらを考慮して、父母の分担額を算出する場合もあります。
事案ごとの検討が必要ですので、弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
離婚後は、婚姻費用(生活費)を請求することができませんので、離婚前に、離婚後の生活設計を立てることが重要です。離婚後の生活設計において、収入確保が重要ですが、離婚時に受け取れる財産等がどれくらいあるか検討し、見通しを立てることも必要になります。
事案によって事情は様々ですので、事案ごとの検討が必要です。
離婚後に安定した生活が送れるよう、離婚時に受け取れる財産等について弁護士に相談することをおすすめします。


