弁護士から連絡を受け取った経験のある方はそう多くはないと思われます。
弁護士からの連絡というだけでも動揺するでしょうし、不安になるでしょう。内容が予想もしていなかった離婚の連絡であればなおさら動揺してしまうことでしょう。自分が責められていると感じて怒り等を覚える方もいるかもしれません。
離婚に応じるにしても、拒否するにしても、自分に不利にならないよう、冷静に対応する必要があります。
なぜ相手の弁護士から連絡がきたのか? 考えられる理由
配偶者が弁護士を通じて離婚の意思を伝えてきた理由として、次の理由が考えられます。
離婚意思の明確な表示
配偶者が弁護士を通じて連絡してきた理由として、離婚の意思が固いこと、離婚の手続を進めることを伝えることにあると考えられます。
交渉を有利に進めるため
離婚にあたっては、離婚そのもののほかに、取り決めることがいくつもあります。財産分与、親権、養育費、面会交流、慰謝料などです。
離婚することや離婚条件について話し合いを有利に進めるには、法的知識や交渉力等が必要になります。
交渉を有利に進めるために、法的知識を有し、交渉に慣れている弁護士に依頼したと考えられます。
感情的な対立を避けるため
本人同士の話し合いでは、感情的になってしまい、話し合いが進まない可能性があります。
感情的な対立を避け、弁護士を介して冷静に話し合うために、配偶者が弁護士に依頼したと考えられます。
離婚の種類と弁護士からの連絡内容
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議離婚の場合
〈協議離婚とは〉
協議離婚とは、裁判所を通さずに、夫婦の話し合いで成立する離婚です。夫婦が合意し、離婚届を市区町村役場に提出することで離婚が成立します。
〈弁護士からの連絡内容〉
配偶者の弁護士から協議離婚について連絡がある場合、一般に、離婚の意思や離婚条件に関する内容が伝えられます。具体的には、次の内容を伝えられることが多いでしょう。最初の連絡では①離婚意思と③連絡方法だけを通知される場合もあります。
①離婚の意思
・配偶者が離婚を希望していることの通知
・離婚の理由等の説明
②離婚条件の提示
離婚条件に関する配偶者の希望が伝えられます。
・財産分与
預貯金、不動産などの取得を希望する財産やその額、自宅に住み続けたいなど財産の分け方についての配偶者の希望が伝えられます。
・慰謝料
あなたからDVやモラハラを受けた、あなたが不倫していたなどを理由に、配偶者があなたに対して慰謝料を請求することもあります。
この場合は、慰謝料請求の理由と請求金額が伝えられることが多いでしょう。
・親権
未成年の子どもがいる場合、親権についての配偶者の希望が伝えられます。
・養育費
子どもがいる場合、養育費に関する配偶者の希望が伝えられます。
・その他に、面会交流や年金分割などについての配偶者の希望が伝えられることがあります。
③交渉の進め方・連絡方法
・交渉・連絡の方法
通常、今後の連絡はすべて弁護士に対してするように伝えられます。また、「配偶者本人やその家族への連絡は控えてください」といった配偶者等への接触・連絡を拒否するとの意思が伝えられます。
・回答期限
配偶者から離婚条件の提示がある場合、通常、配偶者の弁護士から、一定期間内に回答を求められることが多いでしょう。
④法的手続の可能性
協議がまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てると伝えられることもあります。
調停離婚の場合
〈調停離婚とは〉
調停離婚とは、夫婦が裁判所での調停という手続において話し合いを行い、合意により成立する離婚です。
〈弁護士からの連絡内容〉
配偶者の弁護士から、配偶者が離婚を希望していることから、これから離婚調停を申し立てること、あるいは、調停を申し立てたことの連絡がくる場合もあります。
この場合、連絡が届いてから間もない時期に、家庭裁判所から離婚調停の呼出状が届きます。
裁判離婚の場合
〈裁判離婚とは〉
離婚裁判(訴訟)において、裁判官が言い渡す、離婚を認める判決により成立する離婚です。
〈弁護士からの連絡内容〉
離婚については、いきなり裁判を提起することはできず、まず離婚調停を行う必要があります(調停前置主義)。家庭内の問題は、裁判よりも話し合いにより解決することが望ましいと考えられているからです。
離婚裁判が提起される場合、通常、先行して離婚調停が行われており、調停での話し合いでは合意できず、調停が不成立になっています。
配偶者が離婚を強く望んでいる場合、離婚裁判を提起される可能性があります。
配偶者が裁判を提起するにあたり、配偶者の弁護士から連絡がくることは多くはないと思われます。一般に、裁判所から訴状が送られてきて、配偶者が裁判を提起したことを知ることになることが多いでしょう。
いずれの場合でも、配偶者の弁護士から連絡がきたというだけで不利になるということはありませんので、落ち着いて対応することを心がけましょう。
相手の弁護士から離婚の連絡がきた場合の対処法
配偶者の弁護士から連絡を受けたとき、最も大切なのは、「冷静に対応すること」です。知識がないと不安になってしまい、焦ってしまいます。不安を感じたとき、対応に迷うときは、まずは弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。
すぐの回答は避け、まずは内容を確認
離婚問題は、これからの生活に影響する重大な問題です。まずは相手の言い分を正確に理解することが大切です。今後の話し合いや手続において不利にならないように、感情的になって、十分な検討をしないまま回答することはやめましょう。伝えられた内容に理解できない点や判断できない点があれば、弁護士に相談するのがよいでしょう。
〈弁護士からの連絡内容〉
配偶者の弁護士からの連絡が文書(内容証明郵便の場合もあります。)できた場合、弁護士から送られてきた文書には、通常、次の内容が記載されています。内容をよく確認することが大切です。
・題名 「受任通知」、「通知書」、「ご連絡」など
・弁護士の情報
氏名、法律事務所の住所、電話番号等の連絡先など
・依頼された内容と範囲
離婚についての一切の交渉を任されたことなど
・配偶者の方針
離婚を希望することなど
・配偶者の求める離婚条件
財産分与、慰謝料、親権、養育費、年金分割など
・交渉・連絡の方法
相手への直接連絡や接触の禁止、回答方法(たとえば、文書での回答を求めるなど)、回答期限など
〈自分はどうしたいか考える〉
離婚を希望する配偶者の言い分を確認したあと、自分がどうしたいかを考えます。すぐに結論を出す必要はありません。すぐに結論を出せることでもないでしょう。感情的に結論を出すのは、後悔の原因になりかねません。ゆっくりと考える時間が与えられていない場合や、結論が出せない場合は、弁護士などに相談するのがよいでしょう。相談している中で、何を検討すべきか、検討のポイントなどがわかり、考えをまとめる助けになるでしょう。
〈離婚を望まない場合〉
配偶者が弁護士に依頼するまでには、夫婦関係に悩み、考えた時間があったことでしょう。その結果として、離婚を決意し、弁護士に依頼したのでしょうから、その決意は固いと考えられます。
関係を修復するには、まずは、離婚したいと考えた配偶者の気持ちを理解することが大切です。弁護士を通じて伝えられた離婚理由についてよく考え、自分に非がある場合は反省し、誠実に謝罪することが必要だと思います。関係改善の方法を考え、誠実に話し合うことが必要です。
話し合いの際に感情的な言動をすれば、離婚の意思を固める結果を招き、関係修復が困難となります。冷静に対応することが大切です。
考えた結果、離婚を望まない場合、法定離婚事由の有無について確認、検討する必要があります。
あなたが離婚を拒否している限り、すぐに離婚が成立することはありません。協議離婚は、夫婦双方が合意して離婚届を提出しない限り成立しません。調停離婚もどちらか一方が拒否していれば成立しません。それは、弁護士がついている場合も同じです。
しかし、裁判(訴訟)になった場合、法律で定められている離婚原因があれば、あなたが望まなくても離婚が成立することがあります。裁判では、あなたが離婚を拒否しても、離婚を認める判決が出ると離婚が成立します。
裁判で離婚が認められる法定離婚事由として、次のものが法律で定められています。
・不貞行為
・悪意の遺棄
・生死が3年以上明らかでない
・婚姻を継続し難い重大な事由がある
*なお、2024年5月に成立した民法等の一部を改正する法律において、「強度の精神病で回復の見込みがないこと」は離婚事由から削除されることになりましたので、省略します。
法定の離婚事由があれば、裁判となった場合に離婚が成立しますので、離婚を拒否し続けるのがよいのか、配偶者の言い分を踏まえて、もう一度考えることも必要かもしれません。なお、離婚事由があっても有責配偶者からの離婚請求は認められない場合があります。
法定の離婚事由があり、配偶者の離婚の意思が固い場合、配偶者が淡々と手続を進めることもありますので、話し合う時間は多くないかもしれません。今後の進め方を整理・検討するために、弁護士に相談し、法的観点から見た現在の状況・立場、裁判離婚が認められるか見通しを立てることも有益です。
配偶者が勝手に離婚届を出す可能性があるときは、市区町村役場に「離婚届不受理申出書」を提出しておきましょう。これは、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
〈離婚に応じてもいいと考えた場合〉
離婚には反対しない場合、離婚条件を検討し、交渉することになります。 離婚する場合、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流、年金分割など決めなければならないことがいくつもあります。
最近ではインターネット上で情報を集めることができますが、インターネット上の情報は一般的な情報も多く、その内容をご自分のケースに適用できるかどうかの判断が必要であり、その判断には相応の法律知識が必要です。
不利な離婚条件とならないよう交渉を進めるには、弁護士に相談、依頼するのがよいでしょう。
配偶者の弁護士への連絡方法と適切な対応
〈弁護士からの連絡を無視しない〉
配偶者の弁護士からの連絡を受けて、不安を感じる場合や、離婚を拒否したい場合には、対応すること自体を避けたい気持ちになることもあるでしょう。
しかし、配偶者の弁護士からの連絡を無視することは得策ではありません。
連絡を無視すると、解決が遠のくだけでなく、不利な解決になるおそれがあります。
離婚を切り出した配偶者は、夫婦関係について考え、悩み、離婚を決意して弁護士に依頼しています。配偶者が弁護士に依頼した場合、交渉での解決が難しければ、法的な解決を目指し、調停や裁判といった手続を進める意思を有していることが多いでしょう。
協議 → 調停 → 裁判と段階が進むほど、精神的な負担、裁判所への出席などの対応の負担や経済的負担などが大きくなります。
まずは、話し合いでの早期解決を目指し、弁護士からの連絡を無視せず、期限内に連絡するなど対応するのが適切です。
回答期限までに考えがまとまらないこともあるでしょう。その場合は、ご自分も弁護士に相談するのがよいでしょう。配偶者の弁護士には、弁護士に相談中である旨を連絡するという対応も考えられます。
復縁したい場合であっても、配偶者の弁護士からきた連絡を無視することは、誠意のない態度と受け止められ、復縁することが難しくなります。落ち着いて、誠実な対応を心がけましょう。
〈配偶者等に直接連絡しない〉
配偶者に弁護士がついている場合、配偶者本人に直接連絡を取ろうとしてはいけません。
配偶者の弁護士から送られてきた書面には、「配偶者本人やその家族への連絡はしないでください」といった配偶者等への接触・連絡を拒否する内容が記載されていると思います。
弁護士を通じて伝えられた配偶者の考え等が受け入れられず、配偶者はそのように弁護士に言わされているのではないか、本人と直接話せば分かってもらえるはず、配偶者本人と直接話をしたいと思う方も少なくありません。
しかし、配偶者本人に直接連絡することにはリスクがあります。配偶者が、DVやモラハラを離婚理由として離婚を求めてきているケースでは特に注意が必要です。配偶者には連絡しないようにとの要求に反した場合、次のような不利益が生じます。
・自己中心的、共感性が乏しいといった悪い印象を与える。
やはり夫婦を続けることはできないと離婚の意思を強める配偶者もいるでしょう。
配偶者本人に連絡した場合、調停や裁判に手続が進んだときに、DV・モラハラをしていたのではないかという悪い印象を持たれる可能性があります。
・感情的な対立が増し、話し合いが進まなくなる
配偶者が弁護士を立て、弁護士を通じての話し合いを求めてきたのに、直接連絡をとろうとすることは、不誠実であるとの印象を強めることになります。調停や裁判になった際に、相手弁護士は、あなたの不誠実な対応を主張し、あなた自身が調停や裁判で不利な印象をもたれかねません。
交渉の窓口・連絡方法に関する配偶者の求めには、誠意をもって対応しましょう。
〈文書でのやり取りにする〉
電話や対面でやり取りすると、相手弁護士のペースにのまれて、その場での回答や同意を求められたときに、本意ではないのに同意してしまうおそれがあります。
同意や回答を求められても、その場で判断する必要はありません。
しっかりと検討し、納得できる内容を回答することが大切です。
そのためには、検討する余裕を持てる、文書でのやり取りが良いでしょう。
なお、文書でのやり取りは、文書自体が証拠として残りますので、記載する内容には気をつける必要があります。
〈自分も弁護士に相談する〉
相手の弁護士に連絡する前に、ご自分も弁護士に相談することをおすすめします。交渉で不利にならないよう、適切な対応をするには、法律の専門家の助言が重要です。
弁護士に対応を依頼した場合、相手弁護士と交渉する精神的ストレスや負担を軽減することができますし、適切な内容での解決ができる、適切な内容の書面を作成することにより将来的なトラブルを回避できるなどのメリットがあります。
自分も弁護士に相談するメリット
配偶者が弁護士に依頼したことは、法的な準備を整えて離婚手続を進めようとしているサインといえます。
適切に対応するために、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することのメリットとして次のものが挙げられます。
〈精神的な負担・ストレスの軽減〉
相手弁護士とのやりとりをすべて弁護士が行ってくれるため、精神的な負担が軽減されます。
また、法律の専門家が味方につくことで、不安を抑えることができ、冷静な判断・対応につながります。
〈適正な離婚条件での離婚を実現できる〉
財産分与、慰謝料、親権、養育費などについて、法的な観点からも検討を行い、法的に適正な主張が可能となります。
配偶者の主張に適切な反論をすることが可能となります。
〈将来のトラブルを予防できる〉
話し合いがまとまった場合、必要な事項を盛り込んだ適切な内容の書面を作成することができ、将来のトラブルを予防することができます。
〈調停・裁判にも対応できる〉
協議がまとまらない場合でも、調停・裁判(訴訟)まで一貫してサポートを受けることができます。
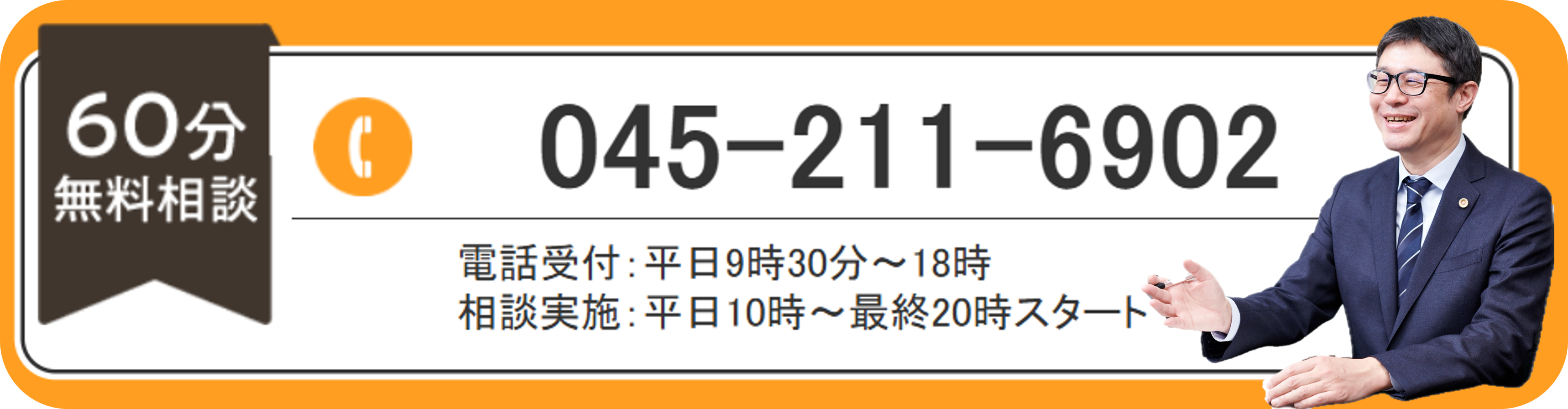
相手の弁護士から連絡がきた際にやってはいけないNG行動
弁護士から連絡がきたとき、気が動転し、焦ってしまうことは仕方ありません。しかし、次のような行動は避けましょう。
感情的な反応や反論
一方的な言い分を聞かされて責められているような気持ちになることもあるでしょう。
そんなときでも、感情的な反応・反論はNGです。感情的な対応は、交渉においても、調停においても、裁判においても、不利になることはあっても有利になることはありません。
相手方が事実と異なる内容を主張している場合、感情的な反論ではなく、ご自身の主張が正しいことや相手方の主張が信用できないこと等を明らかにしていくことが必要です。そのためには、相手方の主張が事実と異なることを裏付ける証拠を提出すること等が必要です。
相手弁護士からの電話に出てしまった場合も、その場で回答する必要はありません。落ち着いて検討するために、相手の言い分を聞くだけにしましょう。口頭で言われたことをその場ですべて理解し、記憶することは簡単ではありません。住所を伝えられる場合は、住所を伝えて相手の言い分について文書で送るように求めましょう。
感情的になって、すぐに結論を出すことは避けましょう。
弁護士との直接(電話・対面での)交渉
相手弁護士と直接(電話・対面で)交渉することは避けた方が良いでしょう。弁護士は法律知識を有し、交渉に慣れているので、相手弁護士のペースで交渉が進んでしまう可能性があります。
インターネットで見つけた情報を参考にしてご自分で交渉する方もおられます。インターネット上の情報が正しい場合であっても、一般的な情報も多く、その内容をご自分のケースに適用できるかどうかの判断が必要であり、その判断には相応の法律知識が必要です。
自分で交渉するとしても文書でのやり取りにするなど、対応についてご自分も弁護士に相談できるようにするのがよいでしょう。
虚偽の主張
たとえば、自分に不利な事実を指摘されたときでも、嘘をついてはいけません。あなたの言い分が事実に反することが判明した場合、虚偽の主張をしたことで、配偶者からの信用を失うだけでなく、ご自分の主張の信用性が失われます。また、慰謝料の増額事由にあたる可能性もあります。
子どもの連れ去り
配偶者が子どもを連れて家を出た場合であっても、配偶者の同意なく子どもを連れ去ることは基本的に違法とされ、不利に働きます。状況や経緯によっては、犯罪行為として刑事処罰を受ける可能性もあります。
子どもが連れ去られた場合、子どもを取り戻すために、家庭裁判所に「子の監護者指定」・「子の引渡し」の手続(調停・審判)を申し立てることを検討しましょう。
自力で子どもを連れ戻すことは大きなトラブルになりかねませんので、行わないようにしてください。
SNSへの投稿
感情的になってSNSに投稿することは避けましょう。
名誉棄損等のリスク、配偶者の信用を失うリスク、裁判手続で不利な証拠になるリスク等があります。
離婚協議を進める際のポイント
離婚条件の整理・検討
離婚にあたって話し合う事項として、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割親権、面会交流などがあります。
ここでは、話し合いが難航することが多い財産分与、慰謝料、親権、養育費について離婚協議を進める際のポイントを説明します。
慰謝料、養育費、財産分与
〈慰謝料〉
・慰謝料とは
慰謝料は、相手方の有責行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求できる賠償金のことです。
慰謝料は離婚の際に必ず支払われるものではなく、どんな場合でも請求できるわけではありません。
・慰謝料が発生する根拠・原因
慰謝料は、不貞行為(浮気・不倫)や暴力・モラハラなどの不法行為・有責行為がある場合に請求できます。
単なる性格の不一致が原因で離婚する場合など、重大な落ち度や責任がない場合は慰謝料を請求することはできません。
また、慰謝料は、夫から妻に支払われるものでもありません。離婚の原因が妻の不法行為・有責行為であれば、夫は妻に慰謝料を請求できます。
・証拠の重要性
離婚慰謝料を請求する場合、有責行為を証明する証拠が重要です。
有責行為について争いがある場合、有責行為があったことを証明できなければ、裁判では慰謝料請求は認められません。
・離婚慰謝料の額
裁判例を参考にすると、300万円程度までの範囲にとどまることが多いようです。
離婚慰謝料の額は事情によって異なります。
慰謝料の増額事由として次のものがあります。
不貞行為の期間が長い、回数が多いなど悪質であること
暴力・モラハラの回数が多い、程度がひどいなど悪質であること
有責行為により、大きな怪我を負った、うつ病になったなど
浮気や暴力を二度としないと約束したのに、約束に違反した
婚姻期間が長いなど
慰謝料請求が認められるのか、どのような証拠があれば有責行為を証明できるのか、請求額は妥当な金額かなど確認・検討すべき点があります。判断が難しい場合、弁護士に相談するのがよいでしょう。
〈養育費〉
・養育費とは
養育費は、子どもと一緒に住んでいない親(別居親)が、子どもと同居して養育している親に支払う子どもの生活費です。
養育費には、子どもが生活するために必要な衣食住の費用、教育費、医療費、娯楽費などが含まれます。
・養育費の算定基準
養育費は、基本的に、父母双方の収入によって算定されます。
裁判所が早見表(養育費算定表)を公開しており、調停や裁判になった場合、算定表に基づいて算出されることが多いです。
算定表は、標準的な額を簡易迅速に算定するためのものですので、個別事情をすべて考慮して作成されているわけではありません。
たとえば、私立学校に通っている場合など、個別事情を考慮して養育費を算定することが必要なケースもあります。
養育費の算定において考慮すべき個別事情の有無等について事案ごとの検討が必要になります。
・子どもの年齢と養育費の金額
子どもの成長に伴い、子どもの生活費も変化します。算定表は、子どもの年齢が「0~14歳」、「15歳以上」と分けて作成されています。
養育費の額も子どもの成長にあわせて考える必要があります。
・養育費の支払期間
期間の目安としては、20歳まで、18歳まで、大学を卒業する22歳までなど、事情・状況に応じて様々です。
〈財産分与〉
・財産分与とは
財産分与には、3つの要素があると考えられています。
①夫婦が共同生活を送る中で築いた財産の公平な分配(清算的財産分与)
②離婚後の生活保障(扶養的財産分与)
③離婚の原因を作ったことへの損害賠償(慰謝料的財産分与)
①清算的財産分与が基本であると考えられています。③慰謝料的要素は財産分与ではなく、別途、離婚慰謝料で話し合われることが多いです。②扶養的財産分与は、清算的財産分与や離婚慰謝料では離婚後の生活維持が難しい場合に補充的に認められています。 ここでは、主に清算的財産分与について説明します。 清算的財産分与について話し合う際には、次のポイントを押さえておくとよいでしょう。
・財産分与の対象となる財産の把握
清算的財産分与の対象となる財産は、「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産」です。
共有名義のものだけでなく、配偶者の名義であっても、ご自身の名義であっても、夫婦で協力して形成・維持してきた財産が財産分与の対象となる財産(共有財産)にあたります。
現金・預金、不動産、自動車、株式、投資信託、保険(生命保険等の解約返戻金)、家財道具などです。 不動産など、その価値を評価することが必要な財産もあります。高額な財産、たとえば不動産をいくらと評価するかによって、財産分与の金額は大きく変わりますので、評価額が争いになることはしばしばあります。
夫婦生活に必要な支出等のために負担した債務、たとえば、住宅ローンなどは財産分与において考慮されます。他方、ギャンブルのためにできた借金など、婚姻生活とは無関係の借金は財産分与において考慮しません。
資産と負債の両方がある場合、資産から負債を差し引いた結果がプラスとなれば財産分与を請求することができます。
なお、未払いの婚姻費用がある場合、財産分与において考慮することができます。
・どの時点の財産を分けるのか
財産分与の対象となるのは、通常、夫婦が結婚してから、協力関係終了時までに築いた財産です。
別居後は、夫婦間に経済的な協力関係がなくなっていると考えられることから、離婚前に別居が先行しているケースでは、通常、別居時の財産が財産分与の対象となります。
・共有財産の確認
財産分与の額を算定するには、まず、財産分与の対象となる共有財産について正確に把握する必要があります。
夫婦とはいえ、配偶者がどのような財産を持っているか分からないことはよくあることです。相手方の財産については、教えてもらっている財産以外にも財産がないか、確認・検討する必要があります。
そのためには、対象となりうる財産をできる限りリストアップし、把握することが必要です。
将来受け取る退職金などを忘れていませんか。銀行、証券会社、保険会社などから郵便物が届いているか確認することも大切です。郵便が届いている銀行等に財産がある可能性があります。 財産のリストアップや把握は、弁護士に相談しながら進めるのがよいでしょう。
・特有財産と共有財産の区別
結婚前から持っていた財産(結婚前に貯めた預金など)は財産分与の対象にはなりません。
親などから贈与された財産、相続した財産も、夫婦の協力により築いた財産とはいえませんので、財産分与の対象になりません。
このような財産を「特有財産」といいます。
離婚時点で、夫または妻の名義の預金があった場合、この預金が特有財産か夫婦共有財産か問題となることがあります。結婚する前に貯めていた特有財産である預貯金に、婚姻後に形成したお金が混ざっている場合もあるでしょう。通帳の記載などから、共有財産ではなく特有財産であることを説明・証明することが重要です。
・財産形成への貢献度
貢献度・寄与度に応じて財産を分けるのが公平だと考えられています。 財産分与の割合は基本的には2分の1です。「2分の1ルール」と呼ばれることがあります。
貢献度・寄与度が明確でなければ同等と推定されます。
夫婦の一方が財産形成に大きく貢献していた場合には、割合が修正されることもあります。夫婦の一方の特別な資格や能力によって多額の財産が築かれた場合は、分与の割合が修正されることもあります。
―――民法改正―――
2024年5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この改正民法は2026年5月までに施行予定です。
改正後の民法768条3項には、「婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」と定められています。
法律では、絶対に2分の1でなければならないと定めているわけではありません。寄与(貢献)の程度が異なるときはその割合で分与することを否定していません。
この改正では、財産分与を行う際に考慮すべき事情が定められました(改正後の民法768条3項)。財産分与を判断する際の考慮事情として、次のものが挙げられています。
① 当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額
② その取得又は維持についての各当事者の寄与の程度
③ 婚姻の期間
④ 婚姻中の生活水準
⑤ 婚姻中の協力及び扶助の状況
⑥ 各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入
⑦ その他の一切の事情
親権
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を決める必要があります。
なお、令和6年に成立した改正民法では、この改正民法の施行後は、共同親権とすることもできるようになります。必ず共同親権になるわけではありません。この改正民法は、令和8年5月までに施行されることになっています。
親権に争いがある場合、裁判手続では、子どもの利益を守ることができる適任者であるかどうかが重視されます。 裁判所が親権者を決める判断要素のうち重要なものとして次のものが挙げられます。
・監護の継続性・母性の優先(主たる監護者優先)
監護していない親が親権者となる場合もありますが、現実に子どもを養育監護している親が優先される傾向があります。監護養育を行ってきた親との関係を切り離すことは、子どもを不安にさせ、心理的不安定をもたらすおそれがあるからです。また、生活環境の変化は子どもに大きなストレスを与えます。そのため、これまで主に子育てを担当してきた親、同居している親が優先される傾向にあります。
現在は、母親を優先するという考え方は取られておらず、母性的な役割を担当する親と子の関係を重視するようになっています。
ただ、子どもが乳幼児の場合、子どもの世話は母親が中心となって行っており、母親が子どもの世話をしている時間等が父親よりも長いことが多く、母親が親権者となることが多いのが実情です。
・子どもの意思
15歳以上の子についてはその意思が尊重されます。
10歳から14歳の子について、その子の意思が反映されます。
子どもは監護養育している親の影響を受けやすい面があり、親の気持ちを察して発言する可能性がありますので、裁判所では子の発言が本心によるものか総合的に判断されます。
よくある質問
弁護士に相談するタイミングは?
弁護士には早めに相談することをおすすめします。
相談することで、法的な観点から状況を整理し、法的な見通しを立てることができます。早めに相談することにより、法的に通らない主張をし続けることで紛争が長期化し、経済的な負担や精神的な負担は増えたけど、希望する解決にはならなかったという事態を避けることができます。
相手弁護士が高圧的な態度をとる場合には、ご自分で交渉することのストレスは大きくなります。依頼者の要求を通すためにあえて強気な態度で接してくるケースもあります。相手弁護士の態度が高圧的な場合も弁護士に相談するのがよいでしょう。
無理な離婚条件を提示されている場合も、弁護士に相談することをおすすめします。相手弁護士から伝えられる離婚条件が法的に適切・妥当であるとは限りません。相手弁護士は自分の依頼者の希望を伝えているだけの場合があります。提示された離婚条件があなたに不利な内容で、もっと有利な解決ができる場合であっても、話し合いでは双方が合意すれば離婚は成立します。無理な要求をされて困っている方は弁護士に相談することをおすすめします。
あなた自身も弁護士に相談し、対応を依頼しても、トラブルが大きくなるわけではありません。
離婚はその後の人生・生活に大きな影響を及ぼします。対等な交渉を行うには、少なくとも、相手と情報の質・量において同等であることが必要です。
相手弁護士から連絡が来た時点で、弁護士に相談するのがよいでしょう。
相手の弁護士と直接話してもいいですか?
相手弁護士と直接話すことは避けた方がよいでしょう。弁護士は専門家として法律知識を有し、交渉に慣れているので、相手弁護士のペースで交渉が進んでしまう可能性があります。
インターネットで見つけた情報を参考にしてご自分で交渉しようとされる方もおられます。インターネット上の情報が正しい場合であっても、その内容がご自分の事案にもあてはまるかの判断が必要ですし、その判断には法律知識が必要です。
たとえば、養育費について、家庭裁判所が参考にしている「養育費算定表」が公表されています。この算定表は簡易迅速に養育費を算出するために作成されたもので、標準的な事情は考慮されていますが、個別事情がすべて考慮されているわけではありません。個別事情に応じた算定が必要なケースもあります。
財産分与についても、適正な財産分与とするには、法的知識は欠かせません。
相手弁護士と直接交渉すると、相手ペースで交渉が進み、感情的になってしまうこともあります。感情的な対応は良い解決にはつながりません。
不利にならないよう、できる限り相手弁護士と直接話すことは避け、文書でやり取りする、ご自分も弁護士に依頼するなど、慎重な行動を心がけましょう。
まとめ
配偶者の弁護士から連絡があったときは、まずは落ち着き、内容をよく確認し、考える時間を確保しましょう。
冷静になって自分の気持ちを考えてみましょう。
離婚したくない場合は、法定離婚事由があるか確認します。夫婦としてやり直せるかについても考える必要があるでしょう。
離婚に応じてもいいと思える場合、離婚条件を検討し、交渉を行います。
いずれの場合も、弁護士からの連絡を無視せず、対応を考えましょう。
配偶者に直接連絡を取ることはNGです。相手弁護士と直接話をすること、交渉の場ですぐに回答や合意することも避けましょう。
交渉において、情報面で不利な立場では、対等な交渉は難しく、不利な結果になる可能性が高まります。このことは、離婚の話し合いでも同じです。
冷静に適切に対応するために、また、法的な見通しを立て、より良い解決となるよう、早めに弁護士に相談するのがよいでしょう。


