このページでは、離婚調停について具体的なイメージが持てるように、手続きの流れ、離婚調停のメリット・デメリット、手続きに必要な書類・費用・時間、ポイントなどについて説明します。
調停離婚とは何か
調停離婚とは
調停離婚は、家庭裁判所の調停という手続きで話し合い、双方が合意することで成立する離婚のことです。
裁判所と聞くとテレビなどで見る法廷を思い浮かべて、厳しい質問がやり取りされている裁判の場面を想像してしまう方もいるかもしれません。
調停は、テレビで見る裁判のイメージとは異なり、話し合いにより当事者の自主的な解決を図る手続きですので、法廷ではなく調停室という非公開の場所で行われます。
離婚調停では、調停委員や裁判官を介して話し合いを行いますので、配偶者と顔を合わせずに話し合うことができます。
離婚についてだけでなく、財産分与、慰謝料、親権、養育費、年金分割などについても話し合いを行うことができます。
別居中の場合は、婚姻費用(生活費)について話し合うことができます(別途、婚姻費用分担請求調停の申立てが必要です)。
感情的になって話し合いが進まないなど、夫婦だけでは合意できなかった問題も、第三者が間に入ることにより話し合いが進んで、合意できる場合があります。
協議離婚との違い
協議離婚も調停離婚も、話し合って、夫婦双方が合意することで離婚が成立する点は同じです。
また、協議離婚でも、調停離婚でも、離婚届を市区町村役場に提出する必要があります。
協議離婚と調停離婚では、次のような違いがあります。
合意内容を記載した書面の効力
調停が成立した場合、裁判所が作成する調停調書という書面には確定判決と同じ法的効力があります。そのため、合意した離婚条件、たとえば、養育費や慰謝料を相手が支払わなかった場合、新たに裁判をすることなく、調停調書を使って、相手の預金や給与などの財産を差し押さえる手続(強制執行手続)を裁判所に申し立てることができます。
協議離婚の場合、離婚協議書を作成していても、強制執行するには裁判等をして判決等を取得する必要があります。
協議離婚の場合でも、強制執行認諾文言付き公正証書が作成されている場合、相手の預金や給与といった財産を差し押さえる手続を裁判所に申立てることができます。なお、たとえば、慰謝料を支払うという合意に加えて、慰謝料を支払う義務を負う人が、支払いが滞った場合には直ちに強制執行を受けてもやむを得ないという文言(これを「強制執行認諾文言」といいます。)が記載された公正証書のことを、強制執行認諾文言付き公正証書といいます。
離婚成立日
協議離婚では離婚届を市区町村役場に提出した日に離婚が成立します。
調停離婚では離婚調停が成立した日に離婚が成立します。
なお、調停離婚の場合も、離婚届を市区町村役場に提出する必要があります。
裁判離婚との違い
相手方の同意
調停離婚では、話し合いにより夫婦双方が合意した場合に離婚が成立します。
他方、裁判離婚では、相手方が同意しなくても、離婚を認める判決により離婚が成立します。なお、裁判の途中で、話し合い(和解)により離婚を成立させることもできます。
離婚事由
調停離婚では、離婚について夫婦の合意が必要ですが、夫婦が合意すれば、法律で定められている離婚事由がなくても離婚できます。
他方、裁判離婚では、離婚が認められるには、法律で定められている離婚事由があることが必要です。離婚事由がある場合には、一方が離婚に応じない場合でも離婚を認める判決により離婚が成立します。ただし、有責配偶者からの離婚請求は認められない場合があります。
調停離婚のメリット・デメリット
メリット
・相手と顔を合わせることなく話し合いができる
離婚調停では、調停委員や裁判官を介して話し合いを行います。調停委員は、夫婦別々に聴き取りを行いますので、夫婦が顔を合わせたり、直接話すことなく話し合いを行うことができます。
・感情的にならず、冷静な話し合いができる
第三者(調停委員)が間に入ることで、感情的になることなく、スムーズに話し合うことができる可能性が高まります。
・自分の考えや気持ちを主張することができる
DV、精神的虐待、モラハラがある場合でも、調停委員を介して話し合いを進めることができ、自分の考えや気持ちを主張することができます。
・強制執行ができる
調停が成立した場合に作成される調停調書には確定判決と同じ効力がありますので、調停調書により、強制執行手続を裁判所に申し立てることができます。
デメリット
・協議離婚に比べると、時間、労力、費用がかかる
調停期日に出席するために裁判所に行く必要があります。
様々な離婚条件について話し合うことになるため、1回の期日で離婚が成立するケースは少なく、何度も裁判所に行く必要があります。
調停は、裁判所や当事者の都合によりますが、1か月に1回程度のペースで行われます。
また、調停は平日の日中に行われるため、仕事をしている人は休みをとる必要がある場合もあります。
・相手が合意しなければ離婚が成立しない
調停は話し合いでの解決を目指す手続きですので、条件について合意できない場合は不成立となり、時間と労力をかけても解決に至らないというケースもあります。
このように、離婚調停にはデメリットもあります。
しかし、感情的になったり、DV、モラハラなどがあり、夫婦での話し合いが難しいケースでは調停を申し立てることにより、調停委員を介して話し合いができ、合意できる可能性があります。
法律で定められている離婚事由がある場合、離婚調停で離婚の合意ができないときには離婚裁判を提起することができます。日本では、原則として、離婚調停を経ずにいきなり離婚裁判を提起することはできず、裁判の前に離婚調停を行う必要があります。これを調停前置主義といいます。
離婚調停の申立ての流れ
離婚調停の流れについて確認しましょう。
① 離婚調停の申立て(申立書の準備と家庭裁判所への提出)
離婚調停は、調停申立書という書面を作成し、一般的には相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して申し立てます。調停申立書は、家庭裁判所の窓口やホームページで入手できます。
申立書と一緒に、必要書類(戸籍謄本など)、収入印紙(裁判所に納める手数料)などを裁判所に提出します。
申立ては、申立書や必要書類を裁判所に持参または郵送して行います。
基本的な費用
・ 収入印紙代 1,200円
・ 郵便切手代 裁判所によって異なりますので、申立てをする裁判所に確認が必要です。
・ 戸籍謄本の取得費用 450円
弁護士に依頼する場合には弁護士費用が必要です。
必要書類
申立てに必要とされている、標準的な書類は次のとおりです。
・ 夫婦関係等調整調停申立書(2通)
・ 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
・ 事情説明書
・ 子についての事情説明書(未成年の子どもがいる場合)
・ 進行に関する照会回答書
・ 連絡先等の届出書
・ 年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)
※ 年金分割のための情報通知書の請求手続きは、年金事務所、各共済組合または私学事業団で行います。
② 調停期日までの流れ
裁判所で申立てが受理されると、裁判所から、調停期日通知書(呼出状)が郵送で届きます。第1回目の調停期日は、申立てから1~2か月程後に指定されます。
③ 調停期日の流れ
調停当日は、指定された時間までに家庭裁判所に行き、受付をして、待合室に行きます。待合室は、申立人待合室と相手方待合室に分かれています。
待合室で待っていると、申立人と相手方が交互に呼び出されて、調停室に案内されます。調停室で、調停委員に離婚に関しての考えや要望、相手方の意見への反論などを伝えて、話し合いを進めていきます。30分程度ずつ、夫婦交互に調停委員と話をします。
財産や収入に関する資料、言い分を裏付ける資料などの提出を求められることもあります。
1回の調停期日は、約2時間です。
1回で解決しない場合、必要に応じて、次の調停期日の日程調整をします。裁判所の混み具合や当事者の都合によりますが、調停は月1回程度のペースで開かれます。
④ 調停の終了(調停成立/不成立)
調停成立
夫婦間で合意ができた場合は調停が成立し、合意した内容を記載した調停調書が作成されます。
調停成立日に離婚が成立します。
調停離婚が成立してから10日以内に、離婚届を調停調書謄本と一緒に市区町村役場に提出しなければなりません。また、年金分割の割合を決めた場合には、年金事務所等において年金分割の請求手続きを行う必要があります。
調停不成立
夫婦間で合意ができない場合、相手方が調停に出席せず話し合いができない場合には、調停は不成立となります。
調停不成立の場合、離婚裁判を提起するか、改めて夫婦で話し合い(離婚協議)をするか、今後の進め方を検討します。
時間をおいて、再度、離婚調停を申し立てることもあります。
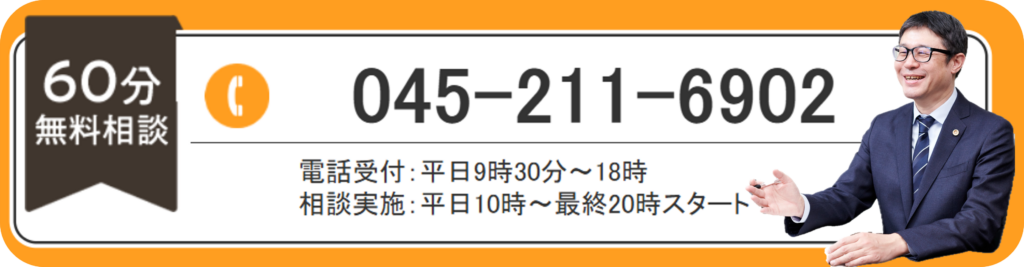
離婚調停で決められること
離婚調停では、離婚そのものだけでなく、次の内容について話し合うことができます。
親権
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を決めなければいけません。
現状では、離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。
なお、令和6年に成立した改正民法では、この改正民法の施行後は、共同親権とすることができるようになりました。共同親権ではなく、単独親権となる場合もあります。
協議により親権者を決めることができます。争いがある場合、子どもの利益を守ることができる適任者であるかどうかが重視されます。
子どもと離れたくないという気持ちが強いことから、親権の争いは激しくなる傾向があります。
調停等では、裁判所に親権者として適切であると分かってもらう必要がありますが、感情的になってしまい、調停の場でも冷静さを欠いて、自分が親権者として適切な要素を備えていることをうまく伝えられないこともあるかもしれません。
そのような場合、親権者の判断に重要な要素、その裏付けとなる事情を適切に裁判所に伝えることができるよう、弁護士に相談することをおすすめします。
養育費
養育費とは、子どもが生活するために必要な費用(衣食住の費用や教育費、医療費、娯楽費など)のことです。
子どもが安定した生活を送り、健やかに成長するには養育費は継続して支払われることがとても大切です。
両親が離婚した後も、別居している親(別居親)から養育費が継続して支払われていることを子どもが知ったとき、子どもは別居親からも愛されていることを感じることができます。別居親からの愛情を感じることができることは、子どもの成長にとってとても重要なことです。
子どもが自立するまで子どもにかかる費用を負担することは親の義務です。
期間としては、20歳まで、18歳まで、大学を卒業する22歳までなど、事情・状況に応じて様々です。
養育費の額は、支払う側と受け取る側の経済力によって変わります。
基本的には、双方の収入を基準に算定します。
裁判所が早見表(養育費算定表)を公開しており、調停等では、算定表に基づいて算定されることが多いです。
算定表は、あくまで標準的な額を簡易迅速に算定するためのものですので、個別事情をすべて考慮して作成されているわけではありません。
例えば、私立学校に通っている場合など、個別事情を考慮して養育費を算定することが必要なケースもあります。個別事情を考慮した算定が必要な場合、その事情を主張する必要があります。
面会交流
面会交流とは、未成年の子どもと別居親が、子どもに会うことやその他の方法で交流することをいいます。
電話やメール・LINEなどでやりとりする、学校行事に参加する、写真やプレゼントを送るなども面会交流です。
会う頻度、時間、場所などは、子どもの年齢、生活環境等を考えて,子どもに負担をかけることのないように十分配慮し、子どもの意思も尊重して決めます。
離婚が成立する前の別居期間中でも、家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
別居親が子どもに暴力をふるうなど不適切な監護養育を行っていた場合など、面会交流を制限・禁止される場合があります。
財産分与
財産分与とは、離婚にあたって、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を分ける制度です。
財産分与は、①夫婦が共同生活を送る中で築いた財産の公平な分配(清算的財産分与)、②離婚後の生活保障(扶養的財産分与)、③離婚の原因を作ったことへの損害賠償(慰謝料的財産分与)の性質があると考えられています。①清算的財産分与が基本であると考えられています。
清算的財産分与の対象は、婚姻期間中に協力して築いた財産です。たとえば、預貯金、不動産、自動車、株式、投資信託、保険(解約返戻金)、退職金などがあります。
離婚前に別居している場合は、通常、別居後は経済的な協力関係がないと考えられますので、別居時の財産が財産分与の対象となります。
結婚する前から持っていた財産、相続により取得した財産、親などから贈与された財産は、夫婦が協力して築いたものではありませんので、財産分与の対象となりません。
夫婦であっても、相手が持っている財産をすべて知っているとは限りません。相手の財産については、教えてもらっている財産のほかにも財産がないか、把握しておく必要があります。離婚を切り出した後や別居後は、相手の財産を確認することが難しくなりますので、離婚を考えたら、早めに相手の財産を把握し、財産に関する資料のコピーや写真をとっておくとよいでしょう。
財産の分け方として、基本的に、貢献度に応じて財産を分けるのが公平だと考えられています。貢献度は基本的には50:50とされることが多いです。「2分の1ルール」と呼ばれることもあります。
ただ、財産分与は半分ずつと法律で決まっているわけではありません。
お互いの合意があれば、50:50ではなく、自由に分けることができます。
分け方についても十分に検討する必要があります。
自宅を購入する際に、親から頭金を出してもらっている場合、結婚する前に貯めた預金から頭金を出した場合など、半分ずつで分けた結果が不公平になる場合もあります。このような場合は、分け方を検討する必要があります。
不動産など、価額を決めるために評価を必要とする財産もあります。
こういった財産評価が必要になるなどの複雑な財産分与では、適正な財産分与をするために、法律知識と交渉力が必要となります。
年金分割
婚姻期間中に納めてきた厚生年金保険料は夫婦が共同して負担してきたと考えられるのに、離婚した夫婦間で(特に、夫が会社員等として働き、妻が家事に専念する夫婦間で)、老後にもらえる年金額に差が生じる不平等を是正する必要があります。その不平等を是正するのが年金分割です。
たとえば、妻が専業主婦だった場合、夫の厚生年金の保険料納付実績を分割することができます。
年金分割の割合の上限は2分の1(50%)です。
離婚調停を行っている場合は、年金分割についても一緒に話し合って決めることが多いです。
調停や審判で分割割合が決まったら、当事者のいずれか一方から、年金事務所等において、年金分割の請求手続を行う必要があります。家庭裁判所の調停や審判に基づいて自動的に分割されるわけではありません。
年金分割の請求に際して、調停調書謄本(審判の場合は審判書謄本及び確定証明書)、戸籍謄本などの提出を求められます。
離婚から2年を経過すると年金分割の請求ができなくなりますので、注意が必要です。
慰謝料
慰謝料とは、相手の暴力や浮気などの不法行為によって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
慰謝料を請求できる不法行為の例としては、DV(家庭内暴力)や浮気(不貞行為)などがあります。
性格の不一致や価値観の違いは、不法行為とはいえず、慰謝料請求できません。
相手が不貞行為やDVなどを認めない場合、相手の不貞行為やDVがあったことについて、慰謝料を請求する側が証明する必要があります。
証明するためには証拠が重要です。
証拠は、離婚を切り出す前や別居前に集めておく必要があります。
慰謝料の額をいくらにするかについて、法律には書かれていません。
慰謝料の額を算定するときに考慮される要素としては、
・離婚原因となった不法行為(有責行為)の内容・程度
・婚姻期間
・精神的苦痛の程度(心身の健康を害したなど)
・請求者側の責任の有無や程度
などといったものが挙げられます。
話し合いで決めるのであれば、慰謝料の額は、夫婦双方が合意した金額となります。
離婚の際の慰謝料について、慰謝料を請求できるか、どれくらい請求できるかということについては、それぞれの事案で検討が必要です。浮気などの証拠の有無によって影響を受けますし、相手がすぐに離婚をしたいと考えている場合に多く支払うケースもあります。
適正な慰謝料を受け取るためにも、離婚を切り出す前に、弁護士にご相談されることをおすすめします。
婚姻費用
婚姻費用(生活費)が支払われていない場合、婚姻費用分担請求調停を申立てる必要がありますが、婚姻費用についても話し合うことができます。
離婚に際しては、様々なことを話し合う必要があります。法律知識などの情報を持たず、また、財産分与に関する資料や慰謝料請求のための証拠など、準備が十分でないまま話し合いを行うと、不利な内容で合意してしまう可能性があります。適正な離婚条件での離婚を実現するために、話し合いを行う前に、弁護士に相談するのがよいでしょう。
離婚調停の基本的な費用
申立手数料:収入印紙1,200円分
郵便切手:裁判所により異なりますので、調停を申し立てる裁判所に確認が必要です。
戸籍謄本取得費用:450円
弁護士に依頼する場合は、着手金、報酬金などの弁護士費用がかかります。
離婚調停を有利に進めるためのポイント・気をつけたいポイント
離婚調停を有利に進めるには準備が重要です。
① 主張(言い分)をまとめておく
調停では、離婚を考えた経緯、希望する離婚条件など、あなたの言い分を調停委員に説明する必要があります。
離婚を決意した理由、現在の夫婦関係、親権・養育費・財産分与・慰謝料に関することは聞かれますので、事前に準備しておきましょう。
② 法定の離婚事由を主張する
法律が定める離婚事由がなくても、夫婦双方が合意すれば調停離婚は成立します。
もっとも、法定の離婚事由があれば、調停での話し合いにおいても有利に働く可能性があります。
法定離婚事由として主に次のものがあります。
・不貞行為
不貞行為とは、自由な意思に基づき、配偶者以外の人と性的関係を持つことです。
・悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦間の義務(同居・協力・扶助義務)を履行しないことをいいます。理由なく別居し、生活費を支払わない場合などです。
病気療養や出張等を理由とする別居や、配偶者の有責行為(DVや不貞行為など)をきっかけとする別居は、正当な理由に基づくといえます。
・その他婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻を継続し難い重大な事由とは、一般に、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない状態をいいます。
DV、モラハラなどがあった場合、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない状態にあれば、離婚事由があると認められます。
③ 証拠・資料の収集
自分の言い分を裏付ける証拠があれば、説得力が増します。調停だけでなく、調停が不成立となり裁判となった場合、証拠が重要です。有力な証拠があれば、相手方も争うことは得策ではないと考え、話し合いが有利に進む可能性があります。
慰謝料の請求が認められるには、相手の不貞行為やモラハラなどを証明する証拠が必要です。
適正な財産分与のためには、相手の持っている財産について確認し、把握する必要があります。
離婚を考えていることが知られてしまうと、警戒されてしまい、証拠を十分に確保できない可能性があります
調停など離婚手続を有利に進めるには、できる限り早い時期から(離婚を切り出す前や別居前に)、資料・証拠を収集し、確保しておきましょう。
④ 調停委員とのコミュニケーション、調停委員に与える印象に気を配る
調停においては、調停委員からどのような印象を持たれるかということについても気を配ることも重要です。
例えば、モラハラされたと相手方が主張しているケースで、あなたが納得できないからといって怒り、不快感を示すなど感情的な対応をしたり、乱暴な発言をした場合には、調停委員は相手方の言い分を信用し、あなたがモラハラをしていたという印象を持ち、あなたの言い分を信用してもらえなくなる可能性があります。そうなると、話し合いを有利に進めることは難しくなります。
また、例えば、派手な服装や高価なブランドを身につけていると、浪費しているという印象を与えかねません。
調停委員に悪い印象をもたれないよう、落ち着いた清潔感のある服装、丁寧な言葉づかいと冷静な態度を心がけましょう。
⑤ 弁護士への相談・依頼
離婚調停は、話し合いをする手続ですので、ご自分で対応することも可能です。
ただし、手続きを自分で進めることができることと、自分が望むように話し合いを進めることができるかは別問題です。
調停が成立してしまうと、あとから不服を申し立てることはできません。
そのため、調停が成立する前に離婚条件等を十分に検討し、納得がいくまで話し合うことが大切です。
離婚調停では、様々な事項について話し合い、法的な判断や財産の評価などが必要な場合があります。
話し合いを有利に進めるためには、自分の言い分を説得的に主張することが重要です。説得力のある主張をするには、法律的に必要な事項、自己に有利な事実や証拠を適切に主張・提出することが大切です。
調停委員や裁判官は、どちらかに有利・不利となる助言をしたり、法律的な相談を受けてくれるわけではありませんので、ご自身で手続きを行うことに不安があるときは、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼するメリットとして次のものが挙げられます。
・主張すべきこと、主張しなくてよいこと等を整理し、戦略を立ててくれる
・裁判所に提出する書面を作成してもらえる(説得力をもった主張をすることができる)
・証拠収集、提出などのアドバイスがもらえる
・相手の主張に対して、論理的に反論してくれる
・法的な見通しにより、譲歩すべき点、譲歩すべきでない点のアドバイスをしてくれる
離婚調停に関するよくある質問
調停は必ず成立しますか?
離婚調停は必ず成立するわけではありません。離婚調停では、調停委員が夫婦の意見を調整し、解決策を提示してくれますが、夫婦双方が合意しなければ調停不成立となります。
離婚調停を成立させるには、次の点に注意するとよいでしょう。
①事前準備をしっかり行う
・主張を整理する
:離婚の理由や希望する条件(財産分与、親権、養育費、慰謝料など)を検討しておきましょう。
・証拠を準備する
:相手の財産に関する資料、不貞行為やDV、モラハラの証拠など、有力な証拠があれば、相手方も争うことは得策ではない考え、話し合いで解決できる可能性が高くなります。
②冷静な態度を保つ
感情的にならず、相手の意見を聞く態度も話し合いにおいては大切なことです。
③調停委員とのコミュニケーションを大切にする
感情的になって長々と話すのではなく、要点をまとめて伝えること、誠実な態度を示すことは、調停委員に信頼されることにつながり、調停が円滑に進みやすくなります。
④現実的な条件を提示する
無理な要求をしないことも大切です。相手に不貞行為があった場合など、感情的になってしまう気持ちはわかりますが、適正な条件を提示することで、合意が成立する可能性が高くなります。
すべての希望を通そうとするのではなく、譲れる部分は譲ることで妥協点を見つけることも時には必要です。
裁判になった場合の見通しをたて、離婚条件について、譲れない部分と譲れる部分を事前に検討し、優先順位を決めておくことも必要です。
調停中の別居は可能ですか
別居することは可能です。
ただし、夫婦には、法律上、同居義務があります。そのため、夫婦が合意したうえで別居するのが原則です。
配偶者の承諾を得ずに一方的に別居することは、「悪意の遺棄」と判断される場合があり、ご自身が有責配偶者と判断されてしまう可能性があります。
DVやモラハラを受けている場合など、やむを得ず家を出る場合もあるでしょう。そのような場合、身の安全を確保したうえで、手紙・メール等で別居を伝えることもあります。ご自分での連絡が難しい場合は、弁護士を通じて連絡することもあります。
なお、別居期間が長期になると、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないとして、裁判で離婚が認められる場合があります。
別居後、婚姻費用の分担、子どもの引き渡し、面会交流などの交渉等が必要になる場合があります。
調停で不利になる発言・対応はありますか
・配偶者の悪口を言う
・矛盾した発言をする
・嘘をつく
・怒ったり、不快感を示すなどの感情的な対応
・配偶者との直接交渉を求める
これらの発言・対応をすると、調停委員があなたに対して悪い印象を持つ可能性があります。
あなたの言い分を信用してもらうために、調停委員に悪い印象を持たれるような発言・態度は控えましょう。
調停の中で、自分が責められていると感じる場面もあるかもしれません。感情的な態度を示したり、乱暴な発言をした場合には、調停委員は相手方の言い分を信用し、あなたの言い分を信用してもらえなくなる可能性があります。感情的な対応は、誤解や対立を生じさせ、話し合いが進まない原因となることもあります。丁寧な言葉づかいと冷静な対応を心がけましょう。
まとめ
離婚調停は、裁判所を利用した話し合いの手続きですので、ご自分で行うこともできます。
納得のいくように話し合いを進めるには、適切に事実を主張する、証拠を提出する、相手方の主張に反論すること等が必要であり、知識、経験に基づいて戦略を立てることも大切です。
そのためには、情報、資料、証拠の収集等の事前の準備が重要です。
離婚の準備は、仕事・家事・育児などを行いながら進めることになりますので、時間の面でも、精神面でも負担がかかります。
一人で準備をすることは負担ですし、一人で準備することが難しい方もおられるでしょう。
離婚により、生活に大きな影響・変化が生じます。
離婚後に、安定した生活を送り、自分らしい人生を送るために、不安や心配があれば、一人で悩まず、弁護士に相談することをおすすめします。


