離婚の際は、離婚後の生活についてよく考えることが大切です。
熟年離婚についても同じです。
特に、専業主婦で、夫の収入で生活している場合は、離婚後は夫から生活費をもらうことができなくなるため、経済的に生活が成り立たなくなるおそれがあります。
熟年離婚において、後悔しないために検討し、準備すべきことなどを説明します。
熟年離婚とは
熟年離婚とは
熟年離婚に明確な定義があるわけではありません。
一般的には、長年連れ添った夫婦が離婚すること、婚姻期間がおよそ20年以上の夫婦が離婚することを指しているようです。多くが50歳以上の夫婦になります。
熟年離婚の特徴
熟年離婚の特徴として、すでに子どもが独立しているケースが多いため、親権、養育費、面会交流といった子どもに関する離婚条件が争いになるケースは少なくなります。
その一方で、婚姻期間が長期に及ぶため、財産分与や年金分割などお金に関する離婚条件の争いが中心となるケースが多いことが熟年離婚の特徴です。
子どもに関しては、大学進学費用について争いになるケースがあります。
財産分与については、支払われる予定の退職金、すでに受け取った退職金が対象になるケースが多くなります。
熟年離婚の原因・きっかけ
熟年離婚では、長年一緒に生活してきた夫婦だからこその離婚の原因・きっかけがありますが、その背後には、残りの人生を考え始め、これ以上はガマンしたくない、自分らしく生きたいという気持ちがあるようです。
原因としては、次のものが挙げられます。
性格の不一致・価値観の違い
夫婦であっても、もともとの性格や育った環境などが異なりますので、少なからず性格の不一致や価値観の違いがあります。性格の不一致や価値観の違いは、熟年離婚に限らず、離婚の理由として多くのケースにみられるものです。
子どもの自立や配偶者の定年退職をきっかけに、これ以上のガマンはできないと考え、自分らしく生きたいと考えて、離婚を切り出す方が多いようです。
一緒に過ごす時間の増加
配偶者が定年退職して一緒の時間が増え、自分の自由な時間がなくなった、行動にいちいち口を出されることにストレスがたまり、それまでは耐えられていたが、ガマンできなくなり、離婚を切り出す方もいらっしゃいます。熟年離婚の特徴の1つといえます。
子どもの自立
子どもが自立するまでは、子どものために離婚せず、耐えてきたが、子どもが自立したことで、ガマンする必要がなくなり、離婚を切り出す方もおられます。
相手の不倫・浮気
配偶者が不倫をしていることは分かっていたが、子どもが自立するまではガマンし、子どもが自立したタイミングで離婚に踏み切る方もいらっしゃいます。
配偶者が現在不倫しているというケースもありますが、配偶者が現時点では不倫をしていない場合でも、配偶者が過去に不倫していたことを理由に離婚を切り出す方もいます。配偶者が現時点では不倫をしていない場合では、離婚を切り出された配偶者は、不倫は過去のことでもう済んだ話と考えている場合も多く、離婚に応じないという態度をとる配偶者も少なくありません。また、過去の不倫については済んだこと、許してもらったことだから、慰謝料は支払わないと主張する配偶者もいます。
モラハラ
モラハラは、性格の不一致と同様に、熟年離婚に限らず、多くのケースにみられる離婚の理由です。子どもの自立や配偶者の定年退職をきっかけに、離婚を切り出す方が多いようです。
配偶者・義理の親の介護
熟年離婚に特徴的なものとして、介護の問題があります。
配偶者や配偶者の親の介護が現実的な問題となったことで、これからの人生を見つめ、この人の介護をしたくないと離婚を切り出す方もおられます。
配偶者から配偶者の親の介護を押し付けられ、その一方で、配偶者が協力もせず、時間を自由に使っている状態が続くと、義理の親の介護が終わったタイミングなどで熟年離婚に踏み切るケースもあるでしょう。
熟年離婚のメリット・デメリット
○メリット
メリットとして次のようなものが挙げられます。
・自分らしく生きることができる
・我慢・ストレスからの解放
・相手の世話からの解放
・相手の親族からの解放
・義両親の介護からの解放
・孤独からの解放
熟年離婚の最大のメリットは、結婚生活による悩み・ストレスから解放され、自分らしく生きることができることにあります。
もともと他人同士が結婚しているので、どの夫婦にも不満や悩みはあると思います。夫婦生活での悩みや不満としては、浮気(過去の浮気も含まれます)、家庭内暴力、モラハラ、浪費、家事をやってくれない、厳しく管理される、自由になるお金がないなど様々です。
熟年離婚を考える夫婦の場合、子どもが自立していることも多く、また、子どもが自立するまで子どもを優先して生活していた方もおられるでしょう。子どもが独立した後、ようやく自由な時間ができ、考える時間ができたことで、結婚生活による悩み・不満・ストレスから解放されたい、残りの人生を自分らしく、納得できるように生きたい、そう思うのも自然なことです。
熟年離婚に限りませんが、配偶者の親族との関係から生じる悩みから解放されるというメリットも挙げられます。熟年離婚では、親の介護が現実的な問題となっている夫婦も少なくありません。特に、配偶者が介護等に協力的でない場合は、不満が積み重なっていることが多いでしょう。また、配偶者の親族との折合が悪く、悩んでいた方もおられるでしょう。
夫婦間で会話が少なく、子どものことを相談しても相談に乗ってくれない、子どものことばかりで自分のことはほったらかしだったなど、一緒に生活していながら孤独を感じていた方もおられると思います。
離婚後は、仕事も趣味も、自分の意思で行動できることが増え、活動範囲が広がり、新たな出合いも増え、孤独から解放されるというメリットもあります。
○デメリット
・経済的な不安
・生活面での不安
・孤独感
長年のストレスから解放されるなどのメリットがある一方で、離婚に伴うデメリットもあります。
熟年離婚では、経済的な不安がデメリットとして挙げられます。特に、結婚後に家庭に入り専業主婦・主夫として配偶者の収入で生活していた場合、離婚後の生活費、老後の資金について不安を感じていると思われます。
離婚後は、婚姻費用はもらえなくなりますので、離婚後の生活費について準備を整えておく必要があります。
離婚後は、それまでとは生活が大きく変わりますので、後悔のないよう、また、生活に困ることがないよう、離婚前に準備しておくことが大切です。
離婚を切り出す前に、財産分与、慰謝料、年金分割などで確保できるお金を確認・検討することが大切です。また、離婚を考え始めた時点や子育てが一段落した時点で、働き始めるなどして生活費確保の準備を進めることも大切です。
結婚している間は家事を配偶者に任せきりにしていた場合、特に男性に当てはまることが多いですが、離婚後は、洗濯、掃除、食事などの身の回りのことは自分でしなくてはなりませんので生活面での負担が増えます。
また、熟年離婚をすると、離婚後は自由な気持ちになるでしょう。もっとも、熟年離婚の場合、子どもが成人して独立していることも多く、離婚後に1人で暮らすことになるケースも多いです。特に、定年退職して社会とのつながりが薄れたり、健康に不安があったり、友人には家庭があるために、友人とは思っていたほど一緒に出かけることができない場合など、想像していたよりも孤独を感じることがあるようです。
後悔しないための準備
離婚のメリット・デメリットを理解し、よく考えた結果として離婚を決意したのであれば、後悔することがないよう、準備を始めましょう。
○離婚後の生活設計
離婚後の生活に困らないよう、生活基盤を整える必要があります。
離婚を考え始めた時点で、まずは離婚後の生活費についてどの程度必要で、どの程度収入を得られるか検討することが大切です。特に、結婚後に専業主婦・主夫となった方は、離婚後にすぐに仕事が見つかるとは限りませんので、生活費を確保するための準備が欠かせません。
また、離婚後に住む場所の確保も大切です。年齢的に民間の賃貸住宅を借りることが難しい場合もあるかもしれません。実家に戻ることなどを含め、離婚後に住む場所について事前に十分に検討する必要があります。
○財産分与
財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分け合うことです。
離婚時にどのくらい財産分与を受けることができるか検討しましょう。
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産です。
財産分与の対象となり得るものとして、次のものが挙げられます。
預貯金
不動産
株式、投資信託など
自動車、宝飾品など
退職金など
別居後は経済的な協力関係がなくなっていると考えられることから、離婚前に別居している場合、別居時の財産が財産分与の対象となります。
結婚する前から持っていた財産は財産分与の対象にはなりません。
婚姻期間中に得た財産であっても、親から贈与された財産や相続した財産は、夫婦の協力により形成した財産ではありませんので、財産分与の対象になりません。
長年一緒に暮らしていても、配偶者のもっている財産について把握していない場合もあります。離婚を切り出すと、財産を隠されてしまうこともあり得ます。別居後に配偶者の財産を調べることは難しくなります。離婚を切り出す前に、また、別居する前に、配偶者のもっている財産について確認・調査しておきましょう。
財産の分け方として、基本的に、貢献度に応じて財産を分けるのが公平だと考えられています。
貢献度は基本的には50:50とされることが多いです。「2分の1ルール」と呼ばれることもあります。
ただ、財産分与は半分ずつと法律で決まっているわけではありません。
お互いの合意があれば、50:50ではなく、自由に分けることができます。
具体的にどのように財産を分けるかが問題となる場合もあります。現金・預金の場合には、簡単に分けることができますが、共有財産が自宅不動産だけの場合で、一方または双方が自宅不動産に住み続けることを希望する場合など、具体的な分け方について話がまとまらないこともあります。
夫婦の共有財産に家、自動車、家財道具、株など、色々なものが含まれると、価値評価や分け方について、検討と話し合いが必要になります。
自宅不動産を購入する際に、親から頭金を出してもらっている場合、結婚する前に貯めた預金から頭金を出した場合など、半分ずつで分けた結果が不公平になる場合もあります。
不動産など、価額を決めるために評価を必要とする財産もあります。
こういった財産評価が必要になるなどの複雑な財産分与では、適正な財産分与をするために、法律知識と交渉力が必要となります。
離婚後に安定した生活を送るためにも適正な財産分与を行うことが重要です。
○年金分割
年金分割は、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績を多い方から少ない方に分割する制度です。年金分割の結果、それぞれが受け取る年金額が変わります。
年金分割により自分が年金をどのくらいもらえることになるのかを確認することも大切です。50歳以上であれば、見込額の照会を希望すると、分割後の年金見込額を知ることができます。照会の手続きは年金事務所で行うことができます。
ただし、年金分割を受けて、もらえる年金の額が増えても、実際にお金がもらえるのは、ご自分が年金を受給し始めてからですので、年金を受給するまでにまだ時間がある場合は、生活費の確保について検討が必要です。
なお、年金分割の手続きは、離婚から2年以内にする必要があります。
○慰謝料
慰謝料は、相手方の行為によって精神的苦痛を受けた場合に支払われる賠償金のことです。
離婚の際に慰謝料が必ず支払われると思われている方もおられるかもしれませんが、どんな場合でも請求できるわけではありません。
浮気や暴力などの不法行為がある場合は請求できます。しかし、性格の不一致が原因で離婚する場合など、相手に重大な落ち度や責任がない場合は慰謝料を請求することはできません。
また、夫から妻に支払われるというわけではありません。離婚の原因が妻の不倫やDVであれば、妻から夫に慰謝料を支払うことになります。
離婚にあたって慰謝料を必ず請求できるわけではありませんので、請求できるかどうか事前の検討が必要です。
○子ども・養育費
未成年の子どもがいる場合、離婚にあたって親権者を決めなければいけません。
まだ自立していない子どもがいる場合には、離婚前に養育費について話し合い、きちんと決めておきましょう。
離婚後、子どもと一緒に暮らす親は、子どもと離れて暮らしている親に養育費を請求することができます。
養育費は、子どもが生活するために必要な費用(衣食住の費用、教育費、医療費、娯楽費など)のことです。
熟年離婚の場合、子どもが大きくなっていて、養育費が問題とならないケースもありますが、大学進学費用など高額になる教育費について話し合っておくべきケースがあります。特に、子どもが大学や私立学校に進学することについて配偶者が反対していた場合など、養育費の請求が認められないケースもあり得ますので、離婚を切り出す前に弁護士に相談するのがよいでしょう。
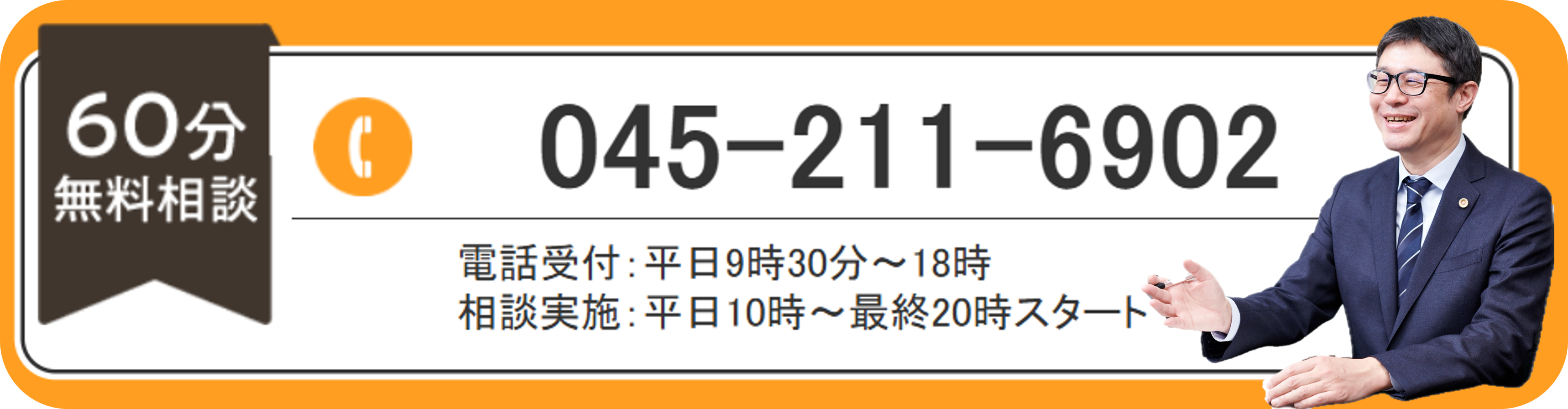
熟年離婚の流れ
熟年離婚の場合も、離婚が成立するまでの流れは他のケースと同じです。
○協議離婚
協議離婚は、夫婦間での話し合いによる離婚です。
協議離婚では、裁判所を通すことなく、夫婦が合意して離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
調停離婚や裁判離婚と比べて、早期に離婚を成立させることができます。
協議離婚では、法律で定められた離婚事由がなくても離婚することができます。また、離婚条件(財産分与、親権、養育費など)を自由に決めることもできます。協議離婚には、このようなメリットがあります。
他方、協議離婚では、配偶者と直接話し合うことになりますので、話し合いによる精神的な負担・ストレスが生じます。
また、夫婦での話し合いでは、感情的になってしまい、話し合いが進まないということもあるでしょう。
離婚にあたっては、離婚するかどうかだけではなく、離婚条件(「お金」と「子ども」のこと)を決めておかなければなりませんし、離婚条件を適正な内容で決めるには法律知識が必要です。相手方のペースで話し合いが進むと不利な条件で合意してしまう可能性がありますので、相手のペースにならないようにしましょう。
離婚条件について合意できたら、合意した内容を法的に効力のある書面として残しておくことも重要です。
○調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所での調停という手続において話し合いを行い、双方が合意して離婚を成立させるものです。
調停での話し合いは、裁判所から選ばれた調停委員(2名)が夫婦双方から別々に話を聞き、話し合いをサポートする形で行われます。基本的に、夫婦が同席して直接話をすることはありません。
1回の調停期日にかかる時間は約2時間です。調停委員が、30分程度ずつ、夫婦双方から別々に話を聞き、通常それぞれから2回ずつ聞きます。
夫婦間で合意できた場合、裁判所がその合意内容を記載した調停調書という書面を作成します。
なお、調停が成立した後、不服を申し立てることはできませんので、調停成立にあたっては、合意する内容・調停調書に記載する調停条項について慎重に検討する必要があります。
調停離婚の場合、調停が成立した日に離婚が成立します。調停成立の日に離婚は成立していますが、10日以内に、離婚届を役所に提出する必要があります。
調停はあくまでも当事者の合意を形成する手続きですので、協議離婚と同様、夫婦間で合意できなければ、調停は不成立となり、離婚は成立しません。
調停が不成立になった場合の対応として、次のものが挙げられます。
①離婚裁判(訴訟)を提起する
②もう一度、夫婦で協議する
③(機会を見て)再び調停を申し立てる
○裁判離婚
裁判離婚は、裁判所の判決により成立する離婚です。
協議離婚や調停離婚との大きな違いは、裁判離婚には、法律で定められた離婚事由が必要なことです。また、夫婦間で離婚の合意ができない場合でも、法律で定められている離婚事由が認められれば、裁判所の判決により離婚が成立することも協議離婚、調停離婚と大きく違う点です。
離婚裁判(離婚訴訟)には強い気持ちが必要になります。離婚裁判で結論が出るまでの期間は、一般的に、約6か月から、長くなると1年から2年程の時間がかかることもあり、協議や調停を含めると長期に及び、精神的な負担も大きくなります。
裁判所の判決に納得がいかない当事者が不服申立て(控訴)するとさらに裁判が続きます。
裁判では、自分の言い分を主張するとともに、証拠を提出します。裁判で有利な判決を勝ち取るには、法律知識が必要不可欠です。裁判をするには弁護士に依頼するのが適切です。弁護士は、離婚を知識面でサポートすることはもちろんのこと、長期戦での精神的な負担を軽減してくれる方がふさわしいでしょう。
離婚裁判が始まった後も、夫婦双方が同意することによって和解離婚という形で離婚が成立することもあります。
法律で定められている離婚事由は以下のとおりです。
①不貞行為
不貞行為とは、自由な意思のもとで配偶者以外の人と性的関係を結ぶこと、いわゆる浮気や不倫です。一時的なものか継続的なものか、愛情の有無は問われませんので、一時的な短期間の性的関係も不貞行為になり得ます。
相手方が不貞行為を認めていない場合、相手方の不貞行為を証明する必要がありますので、証拠が重要となります。
②悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務を正当な理由なく果たさないことです。
浮気相手と暮らすために配偶者や子どもを放置して別居することや収入がありながら生活費を支払わないような場合です。離婚原因としての遺棄が認められるには、遺棄の状態がある程度の期間継続していることが必要です。
別居など、形式的には同居協力扶助義務に違反するような行為があっても、正当な理由や合意に基づく場合は、悪意の遺棄にはあたりません。たとえば、病気療養や介護を理由とする別居、出張等を理由とする別居、配偶者の有責行為(DVやモラハラなど)をきっかけとする別居は、正当な理由に基づくといえます。
③3年以上の生死不明
生死不明とは、配偶者からの連絡が途絶えて、生存・死亡のいずれも不明な状態が継続していることです。
なお、配偶者が7年以上生死不明である場合、失踪宣告制度により、法律で死亡したものとみなされ、婚姻関係は配偶者の死亡により終了します。
④回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったというだけでは認められず、医師の診断(鑑定結果)、離婚後の配偶者の療養・生活などを含めて裁判官が離婚を認めるか厳格に判断する傾向にあります。
なお、法律(民法770条1項4号)では、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない」ことを離婚事由として挙げられていますが、令和6年に成立した民法改正法により、この条項は削除されることになりました。
⑤その他の婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻を継続し難い重大な事由とは、一般に、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない状態をいいます。
別居、性格の不一致、配偶者の親族との不和、多額の借金、過度の宗教活動、暴力(DV)、モラルハラスメント、浪費、犯罪行為、性交渉の拒否・性交不能などを理由に離婚を求める場合、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合に該当するか、裁判官が判断します。
性格の不一致については、多少の不一致はありますので、性格の不一致だけで離婚事由になるのはよほどの場合と考えられます。通常、多くのケースでは、いくつかの要素が重なって婚姻を継続し難い重大な事由にあたると判断されることになります。
なお、①から④の具体的な離婚原因がある場合でも、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには、離婚の請求を認めないとすることができます。
また、夫婦間の婚姻共同生活を円満に維持・継続させる義務を怠った有責配偶者(たとえば、自ら不貞行為を行った配偶者)からの離婚請求については、婚姻関係が破綻している場合でも離婚が認められない場合があります。
有責配偶者からの離婚請求については、次の要件を検討します。
①相当長期間の別居
相当長期間かどうかは、夫婦の年齢や同居期間との対比等で検討します。別居期間が10年を超えれば、通常、相当長期間の別居にあたると判断されることが多いようです。別居期間が10年に満たない場合、特に、婚姻期間が数十年に及んでいる夫婦の場合には、どの程度の別居期間があれば有責配偶者からの離婚請求が認められるかは、事案によって異なります。
②未成熟子の不存在
未成熟子とは、子どもが経済的、社会的に自立して生活することができない状態にあることをいいます。未成年とは異なりますので、成年になっていても未成熟子にあたる場合があります。
未成熟子がいる場合でも、有責配偶者の離婚請求が認められる場合があります。
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるなど離婚請求を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと
次のような事情が考慮されます。
・配偶者の年齢、健康状態
・配偶者の収入、資産
・別居期間中の婚姻費用(生活費)の支払状況
・離婚の際の慰謝料、財産分与
離婚裁判では、判決により決着がつきます。判決に不服がある場合は上級裁判所に不服申立て(高等裁判所に控訴・最高裁判所に上告)することができます。自分の希望どおりの結論でなくても、判決に従わなければなりません。なお、最高裁判所は法律の解釈をする場ですので、浮気などの事実について争えるのは高等裁判所までです。
有利な内容の判決を得るためには、自分に有利な主張や証拠を適切に提出することが必要です。訴えられた場合も、適切な反論と証拠の提出が必要です。裁判を有利に進めるために、早い段階から弁護士に依頼することが良いでしょう。
よくある質問
離婚以外の選択肢はありますか?
離婚のメリット・デメリット等を検討した結果として、離婚を決意できない人もいるでしょうし、離婚のタイミングはもう少し時間が経ってからという人もいるでしょう。
離婚以外の選択肢としては、次のものが考えられます。
・夫婦関係の改善
離婚はせずに配偶者と一緒に生きていくと考えた場合、ガマンやストレスから解放されるために、夫婦関係の改善を図ることが考えられます。
自分では上手く話ができないという場合は、家庭裁判所の調停(夫婦関係調整調停(円満調停))を利用する方法がありますし、夫婦関係のカウンセリングを利用することも検討してみてはいかがでしょうか。
円満な夫婦関係を回復するための話し合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
ただ、夫婦関係調整調停については、離婚調停として申し立てたところ、円満調停で終了する場合もありますし、逆に、円満調停として申し立てたが離婚が成立して終了する場合もあります。配偶者が離婚を選択肢の1つとして考えている場合、調停をきっかけに離婚へと進むリスクもありますので、調停の申立てにあたっては、配偶者の考えを理解しておくことが大切です。
・家庭内別居
話し合いでの関係改善は難しいが、離婚も決意できない場合、家庭内別居が選択肢として考えられます。
同じ家に住みながら、食事や家事を分けて、別々に生活することで、自分の時間を確保し、自分らしく生活することができるようになるでしょう。また、夫婦関係を見直すきっかけとなることもあるでしょう。
・別居
一緒に暮らしている中では夫婦関係の改善が難しく、家庭内別居では精神的ストレスが減らないといった場合、離婚の前に、まず別居してみることも選択肢となります。
別居することで、離婚後の生活をイメージすることができるようになりますし、夫婦関係を見直すきっかけとなることもあるでしょう。
別居により、夫婦関係が改善されることもありますが、離婚に向けて進んでいくこともありますので、離婚に向かって進んでいった場合に慌てないよう、別居前に離婚を見据えた準備をすることが大切です。
熟年離婚では、慎重に検討すること、事前の準備が大切です
熟年離婚をした場合、離婚後の生活でお金がなかったり、仕事が見つからないなどで苦労する可能性があります。また、孤独を感じることも、自分自身の介護について考える時期がきて不安になることもあるでしょう。
離婚後に「こんなはずではなかった」と後悔することがないよう、離婚後の生活を具体的にイメージし、生活が成り立つか検討することが重要です。
熟年離婚では、親権について争いのあるケースが減る一方、婚姻期間が長いことから財産が形成されているケースが増えます。退職金を含む財産分与について、配偶者が持っている財産を把握するなど、適切な内容で財産分与を行うための準備が必要となります。
財産分与などの離婚時に得られるお金だけで離婚後の生活が成り立つというケースは多くはありませんので、離婚後の生活費・収入をどのようにして確保するかについても考え、準備を進める必要があります。
離婚を後悔しないために、自分らしい豊かな人生を送れるようにするために、事前の準備が不可欠です。離婚を考え始めたら、一人で抱え込まず、できる限り早い時期に専門家に相談することをおすすめします。


