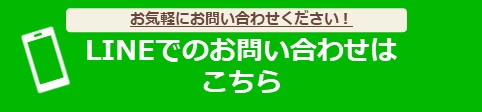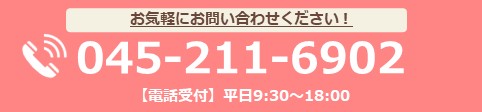「お前は何をやってもダメだ」
「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」
「どこに行くか毎回報告しろ」
などと配偶者から言われて、つらい思いをし、離婚を考えている方がいるのではないでしょうか。
ここでは、モラハラをする配偶者と離婚するために知っておくべきことや注意点を解説します。
モラハラとは何か?(離婚との関係性を理解)
○モラハラの定義と種類
〈モラハラとは〉
モラルハラスメント(モラハラ)とは、言葉や行動、態度で相手に精神的苦痛を与えることをいいます。精神的な嫌がらせです。
次のような発言や態度がモラハラの例として挙げられます。
・人格を否定:「お前は何をやってもダメだ」、「そんなこともできないのか?」
・支配的な発言:「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」
・無視や冷たい態度:「話す価値もない」、「勝手にすれば」、長期間口をきかない
・過度な束縛:「どこに行くか逐一報告しろ」、行動を細かくチェックして自由を奪う
・感情を利用したコントロール:「お前のせいでこんなに辛い思いをしている」と罪悪感を植え付ける
・価値観の押し付け:「普通はこうするべきだろ」、「常識的に考えて○○だろ」
・比較して貶める:「○○さんの方が優秀だ」
内閣府男女共同参画局では、DVの一態様としての精神的な暴力として次の例が挙げられています。
参考:https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/dv/02.html
・大声でどなる
・「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょうなし」などと言う
・実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする
・何を言っても無視して口をきかない
・人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
・大切にしているものをこわしたり、捨てたりする
・生活費を渡さない
・外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする
・子どもに危害を加えるといっておどす
・なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかす
※生活費を渡さない、もしくは仕事を制限するといった行為は、「経済的なもの」と分類される場合もあります。
〈モラハラの特徴〉
モラハラの特徴は、身体的な暴力を伴わないことです。そのため、証拠を集めることが難しいことも特徴です。
発言した場面によって発言の意味合いが変わることもありますので、モラハラに当たるかどうか、判断が難しいこともあります。
モラハラは、被害者が気付きにくいことが多く、つらい、苦しいと感じたら早めに相談することが大切です。
○モラハラが離婚原因となるケース
裁判で離婚が認められる事由(離婚事由)が法律(民法)に定められています(①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと)が、モラハラは具体的な離婚事由としては挙げられていません。
民法では、具体的な離婚事由のほかに、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を抽象的な離婚事由として定めています。
配偶者によりモラハラが行われ、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められれば、裁判で離婚が認められます。
「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうかは、一般に、婚姻関係が破綻しているかどうかを基準に判断されます。法律上の離婚事由となるには、婚姻関係が客観的に破綻状態にあることが必要です。夫婦の一方が配偶者との婚姻生活を続けたくないと主張するだけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとはいえません。
モラハラを理由として離婚するには、相手方の言動・態度を具体的に主張し、相手方の言動等を証明する証拠を提出できるようにすることが重要です。
なお、話し合いで離婚(協議離婚、調停離婚)する場合は、法律上の離婚事由がなくても夫婦が合意すれば離婚することができます。法律上の離婚事由が必要になるのは、裁判で離婚する場合です。
○モラハラによる離婚で有利になる証拠とは
〈モラハラの証明〉
モラハラがあった場合、その内容・程度によっては、離婚や慰謝料を請求することができます。
トラブルや争いが発生したときに問題となるのは、どのような出来事が発生したかという事実関係ですが、事実関係が重要になるのは、モラハラを理由に離婚や慰謝料を請求する場合も同じです。
モラハラがあったという事実については、モラハラを理由として離婚や慰謝料を求める被害者側が証明する必要があります。
夫婦間のモラハラの多くは家庭内で行われるため、客観的な出来事(事実)として何があったのかが、第三者からは分かりにくいという特徴があります。また、モラハラは身体的な暴力を伴わないため、証拠を集めることが難しいことがあります。
〈証拠の重要性〉
モラハラした側は、そんなことはしていないとモラハラ行為を否定することが多いでしょう。証拠がなければ、調停や裁判でも、言った言わないの水掛け論になることも少なくありません。 離婚や慰謝料を請求する被害者が、モラハラがあったことを証明できない場合、離婚請求や慰謝料請求は認められません。
モラハラを行う人には、外面が良い人も多く、離婚調停でも調停委員には良い顔をするため、モラハラ配偶者からされたモラハラ行為についてのあなたの伝え方や説明が不十分で調停委員に理解してもらえないという場面も少なくありません。
自分が受けたモラハラの内容を整理して説明し、第三者(調停委員や裁判官)に理解してもらうことは簡単なことではありません。
そこで重要となるのが証拠です。
証拠は、裁判において重要な意味を持ちますが、それだけではありません。有力な証拠があれば、モラハラを行った配偶者に対し、裁判になった場合の結末を理解させ、争うことは得策ではないことを理解させる材料ともなりますので、話し合いによる早期解決(協議離婚、調停離婚)の可能性が高まります。証拠は離婚問題を早期に解決する手段としても重要な意味を持ちます。
〈モラハラの証拠〉
モラハラを受けている場合、まず、配偶者によるモラハラの証拠化を考えましょう。
次の点から整理し、証拠を残すと良いでしょう。
① いつ
開始時期、モラハラが行われた日時のほか、頻度も重要です。
② どのような場面で
口げんかの中で感情的になり、一時的にお互いに強い言葉を投げかけることは、離婚や慰謝料請求の理由としてのモラハラにはあたらない場合が多いでしょう。どのような場面での言動かということが重要となります。
③ どのようなことを言われたか、どのようなことをされたか
④ ③の言葉、行為、態度で、どのように感じたか
証拠としては、次のものが挙げられます。
・ モラハラを受けているときの録音、録画
モラハラされている場面の音声や動画があれば有力な証拠となります。
怒鳴り声、侮辱的発言などが留守番電話に残されていれば、証拠として保存しておきましょう。
モラハラ行為自体を録音・録画できなかったとしても、配偶者が物を投げつけて壁に穴をあけたり、家具等を壊したりしている場合には、その被害状況を撮影しておきましょう。
・ メールやLINE等の保存
メールやLINEなどのSNSにモラハラの証拠となるようなやり取りが残っていれば、画面をスクリーンショットする、写真を撮るなどして証拠として残しておきましょう。モラハラの内容だけでなく、頻度も重要となりますので、いつ送られてきたのか分かるように、日時が分かる形で残しておくようにしましょう。
・ 日記やメモ
いつ、どのような内容のモラハラを受けたのか具体的な記載のある日記やメモもモラハラの証明に役立つことがあります。モラハラ行為をできる限り具体的に記載しておくのが良いでしょう。ノートや手帳に書いたものだけでなく、スマホやパソコンに保存した記録でも問題ありません。配偶者に見つけられて、捨てられたり、データを消されたりすることもありますので、相手に知られない場所に保存するなど、保存方法に工夫が必要です。信頼できる友人や家族に送った相談などのLINE等も証拠になることがありますので、いつの出来事か、また、いつ送ったのか分かるように、日時が分かる形で残しておきましょう。
・ 医師の診断書、診療記録等
モラハラを受け、ストレスから、食欲不振、無気力、不眠などといった症状が現れることがありますし、抑うつ状態(気分が落ち込み、憂鬱な気持ちが続く状態)、うつ病、適応障害などになることもあります。
そのような場合は、通院し、医師の診断書を取得します。
医師の診断書や診療記録で、配偶者によるモラハラ行為を証明することは難しいですが、あなたの心身が復縁できるような状態ではないことを、相手方や裁判所に説明・説得する資料となります。
・ 警察や公的な機関への相談記録
警察や公的機関(自治体の相談センター等)にモラハラの相談をした事実も証拠となる場合があります。公的機関に相談した内容が書面で保管され、それらの写しを取得することができれば、日記やメモ等の記録や他の証拠と組み合わせて、モラハラの事実を証明することができる場合もあります。
・ 第三者の証言等
モラハラ行為が親族や友人等の面前で行われた場合、モラハラを目撃した第三者の証言は証拠となり得ます。
モラハラの証拠は、モラハラ行為を客観的に証明できるものが重要です。そうはいっても、決定的な証拠を確保することが難しいこともあります。焦らず、まずは、決定的な証拠を残すという姿勢よりも、小さくても数多くの証拠を残すという姿勢が良いでしょう。
○離婚を切り出す前に、別居する前に、証拠の確保を。
モラハラをする配偶者と一緒に生活することは、精神的につらく、早く離れたいと思う方も多いことでしょう。離婚の際には、財産分与等についても取り決めますので、財産分与等に関する証拠・資料も確保する必要があります。
離婚を切り出した後や別居した後は、証拠や資料の確保が難しくなりますので、できる限り早い段階で弁護士に相談し、アドバイスを受けて証拠・資料を確保し、別居に進めるよう準備することが大切です。
モラハラで離婚する方法
○協議離婚
〈話し合い〉
まずは夫婦で話し合い、離婚協議を試みるのが通常の流れです。
しかし、モラハラ配偶者は、こだわりが強い、自己愛が強い、疑い深い、独善的である、共感力が弱い、嫉妬深い、人のせいにする、プライドが高い、などの特徴を持っていることが多く、対等な立場で話し合いを進めることが難しいことが多いでしょう。
モラハラを行っている本人が、自分の言動があなたを傷つけているということを認識していないケースもあります。そのような場合、自分の言動によって、あなたが深く傷つき、関係を修復することが難しいと理解すれば、離婚に応じてもらえることもあるでしょう。モラハラを行う人にはプライドの高い人が多い傾向があるので、話し合いでは、相手を責めるような言い方は控えるなど慎重に言葉を選ぶ必要があります。
しかし、現実的には、モラハラがある夫婦間では、冷静な話し合いができないことも多いでしょう。モラハラを行う人は、自分とは異なる考えや価値観を認めない傾向がありますので、話し合いによる解決が難しいことも少なくありません。離婚を切り出されると、配偶者が「誰のおかげで生活できているとおもっているんだ……」などと暴言を吐くこともあるでしょう。
冷静な話し合いができない場合は、弁護士に依頼し、相手と協議してもらうのが良いでしょう。
〈法律の専門家への相談〉
モラハラに限らず、慰謝料請求や離婚を考えたら、まず専門家に相談することをおすすめします。
離婚を切り出した後や別居した後では、証拠を確保することが難しくなります。
相談する時期が早いほど離婚に向けた適切な準備を行うことが可能となります。離婚や慰謝料の請求には、証拠が重要ですし、その証拠は離婚を切り出す前や別居の前に確保する必要があります。
相手から、理由もなく勝手に家を出て行ったと言われることもあります。法律上、夫婦には同居・協力・扶助義務がありますので、理由なく別居すれば、離婚時に不利になるおそれもあります。別居する理由(モラハラ)があったと主張するためにも、別居前にモラハラの証拠を確保することが重要です。
また、離婚にあたっては、慰謝料の他にも検討すべき離婚条件(財産分与、親権、養育費等)があります。 別居後や離婚後の生活設計も重要です。
早い時期から専門家のアドバイス・サポートを受けながら準備をすることが、希望する条件での離婚や離婚後の安定した生活につながります。
〈別居の検討・準備〉
モラハラ被害を受けている方は、離婚協議を行う前に、別居を検討することが多いでしょう。
モラハラを行う配偶者は、支配欲や執着心が強いことが多く、別居することを認めない場合もあるでしょう。事前に別居することを伝えると、反対されてスムーズに別居できない可能性があります。別居に際しては、相手に知られないように慎重に準備を進めましょう。
別居を検討した場合、別居後の住居と生活費の確保が重要です。
・別居後の住居の確保
配偶者がつきまとい行為を行う可能性がある場合は、住居選びの際に、セキュリティ設備の有無も考慮する必要があります。
子どもがいる場合、別居後の子どもの心情・状況についても考える必要があります。転園や転校は子どもに心理的な負担となることから、可能であれば転園・転校しない形での別居が望ましいでしょうが、安全確保のため転園や転校する場合には別居前の手続きを忘れないようにしましょう。
相手方に伝えることなく子どもを連れて別居した場合、相手方が事態を理解できず、子どもの通う保育園・幼稚園や学校に問い合わせをすることや、待ち伏せして子どもを連れて行くことも考えられます。このような事態の発生を避けるため、別居の前に、子どもの通っている園や学校・施設に事情を説明しておくとよいでしょう。
・別居後の生活費の確保
配偶者に請求できる婚姻費用(生活費)がどのくらいの金額になるか、その目安が重要です。
婚姻費用の金額は、双方の収入を基準に算定します。裁判所が早見表(婚姻費用算定表)を公開していますので、参考にするとよいでしょう。算定表は簡易迅速に婚姻費用を算出するために標準的な事情を考慮して作成されていますが、個別事情を考慮して作成されているわけではありません。個別の事情により増減できる場合がありますので、弁護士に相談するのがよいでしょう。
別居後の児童手当の受給者をご自身に変更する手続きなどについて市区町村役場に相談・確認することも大切です。離婚前であるため、離婚協議中であることの証明を求められる場合もあります。
・証拠・資料の収集
別居の前に行っておくべき重要なこととして、証拠の収集・確保があります。
別居した後は、証拠を集める手段・方法が限られます。
モラハラの証拠、財産分与に関する資料などを別居前に確保するようにしましょう。
〈別居の実行〉
・別居することの通知
事前に別居を伝えずに別居した場合、あなた(と子ども)がいなくなったことに気付いた相手方が、事態を理解できず、突発的な行動にでることもあります。
相手方が突発的な行動にでないように、別居の際に置き手紙をしたり、弁護士に依頼している場合は別居と同時に弁護士から離婚協議を申し入れる文書等が相手方に届くようにしておくのがよいでしょう。
・婚姻費用(生活費)の請求
別居後、婚姻費用を請求します。
モラハラをする配偶者は、プライドが高く、独善的で共感力が弱いこと等から、嫌がらせのため等、婚姻費用を支払ってくれない可能性があります。 また、婚姻費用は金額が争いになることも少なくありません。
相手方が婚姻費用を支払ってくれない場合は、速やかに家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てるのがよいでしょう。
裁判所の実務では、婚姻費用は、請求をした時(通常は婚姻費用分担調停または審判の申立時)から、相手方に支払義務が生じるとすることが多いようですので、速やかに申し立てられるよう別居前に弁護士に相談するなど準備をしておきましょう。
○調停離婚
配偶者との話し合いが難しい場合、離婚調停を申し立てる方法もあります。
〈調停離婚とは〉
調停離婚は、家庭裁判所での調停という手続きで話し合いを行い、夫婦が合意して成立する離婚です。
〈離婚調停とは〉
離婚調停は、家庭裁判所で、第三者である調停委員を介して話し合いを行う手続きです。離婚調停での話し合いは、当事者が交互に調停室に入り、調停委員を介して行われますので、相手方と直接顔を合わせることなく、話し合いを行うことができます。調停は、話し合いで解決を図る手続きですので、協議離婚と同様に、夫婦双方の合意がなければ離婚は成立しません。
調停委員は、中立の第三者として双方の言い分を取り次ぎ、ときには調停委員会としての見解を示して、合意ができるように調整に努めたりします。
〈離婚調停を有利に進めるには〉
調停委員にモラハラの事実を理解してもらうには、調停委員に理解してもらえるよう説明し、その証拠を示す必要があります。具体的な言動や場面がわからないと、調停委員には何が起こったのかイメージできないこともあるでしょう。
モラハラを行う人には、外面が良い人も多く、離婚調停でも調停委員には良い顔をするため、説明が不十分な場合、調停委員には夫婦げんかとして受け取られ、理解してもらえないことも少なくありません。
離婚調停を有利に進めるには、相手方の言動などを具体的に調停委員に説明できるようにし、その証拠を収集するなどの事前の準備が大切です。
〈調停で合意できなかったら〉
調停では、合意できなければ離婚は成立しません。夫婦の一方が離婚を強く求めている場合、裁判(訴訟)により解決を図ることになります。
○裁判離婚
〈離婚裁判(訴訟)〉
離婚裁判では、夫婦間で離婚の合意ができなくても、法律で定められている離婚事由が認められれば、裁判所の判決により離婚が成立します(裁判離婚)。離婚裁判において、財産分与や養育費の支払い、年金分割についても求めることができます。
裁判(訴訟)で離婚が認められるには、民法に定められた離婚事由が必要です。モラハラでの離婚では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」、すなわち婚姻関係が破綻していることが必要です。
〈モラハラの証明〉
この婚姻関係が破綻していることは、離婚を求める側、モラハラの被害者側が証明する必要があります。裁判(訴訟)において、証拠はとても重要です。
モラハラなどの過去にあった事実は、当事者ではない第三者には、その事実があったかどうかも分かりません。第三者である裁判官に、モラハラがあったこと、配偶者のモラハラにより婚姻関係が破綻し、修復の可能性がないことを理解してもらう必要があります。そのためには、配偶者によるモラハラの具体的な内容(言動・態度)といった事実関係を主張し、その出来事があったことを証明する証拠を提出することが重要です。
〈事前準備の重要性〉
裁判(訴訟)では、判決により結論がでます。自分に不利な内容の判決であっても従う必要がありますので、入念な準備が必要不可欠です。
裁判に向けた準備は、離婚を考えたとき、別居を考えたときから行う必要があります。 モラハラの証拠が簡単に集められないこともあり、また、離婚を切り出した後や別居した後は、証拠を集めることが難しくなります。
財産分与の対象となる財産についても、事前に証拠・資料を集めておくことが大切です。夫婦といえども、相手方の持っている財産を把握していないことも少なくありません。離婚を切り出す前や別居前に、できる限り相手方の財産について資料を集めておきましょう。
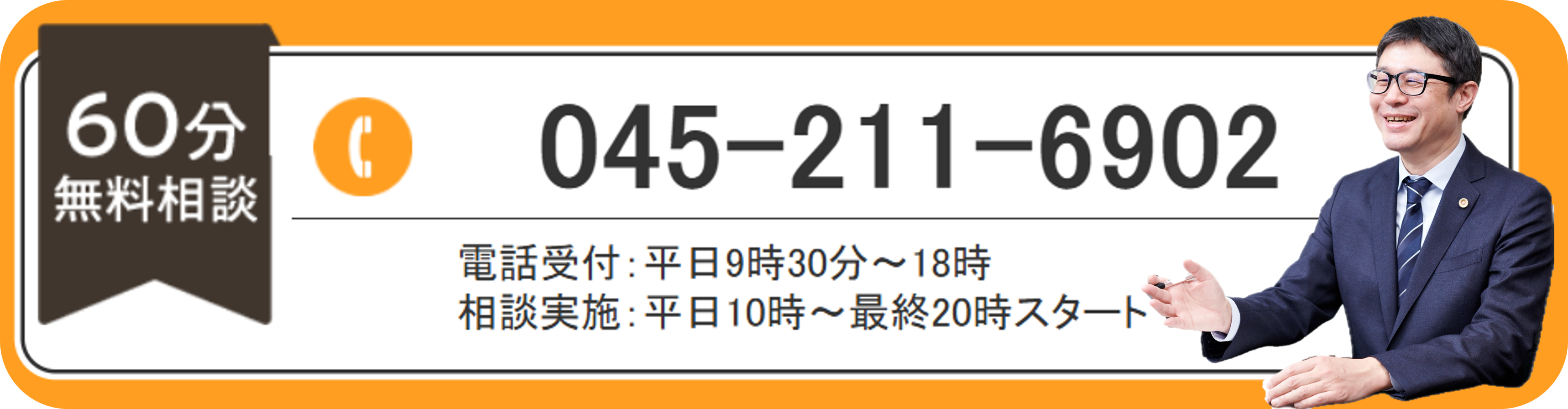
モラハラ離婚で慰謝料請求はできる?
モラハラを受けた場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料とは、精神的苦痛を受けた被害者に対して支払われるお金(賠償金)です。
○慰謝料の相場
〈相場はいくら?〉
慰謝料の額をいくらにするかについて、法律に書かれていません。
モラハラによる慰謝料は、モラハラ行為の回数や内容、被害者が受ける精神的損害の程度、婚姻期間の長さなどの個別の事情により慰謝料の金額は異なります。
モラハラが原因で離婚する場合の慰謝料のおおよその目安は、数十万円~200万円程度になります。この相場は、裁判官が判決で慰謝料の額を決めるときの相場です。
〈慰謝料額の算定要素〉
内心の問題である精神的苦痛の大きさを金銭に換算することは簡単ではありません。精神的苦痛を感じやすい人に支払われる金額が多くなり、感じにくい人には金額が少なくなるというのでは公平ではありません。そこで、どのような行為や言動があったのかによって慰謝料の金額を算定するという考え方が採られています。
モラハラの慰謝料が高額になる要素として、次のようなものが挙げられます。
・モラハラを受けた期間が長い
・モラハラ行為の回数が多い、頻度が高い
・モラハラ行為の悪質性が高い
・モラハラによって、うつ病等の精神的な症状・疾患を発症した
○慰謝料請求に必要な証拠
モラハラを理由に慰謝料を請求するには、証拠によりモラハラがあったことを証明しなければなりません。
暴力を振るわれてケガをした場合は目で見える傷が残りますが、モラハラの場合は、目で見えるような傷跡が残りません。モラハラには、証拠が残りにくい、集めにくいといった特徴があります。
証拠が少なかったり、有力な証拠がなければ、夫婦げんかの範囲内であるのか、モラハラなのか判断できない場合もあります。
できる限り多くの証拠をこつこつと積み重ねることが大切です。
具体的には、次のようなものがモラハラの証拠となります。
・ モラハラを受けているときの録音、録画
・ 配偶者から送られてきたモラハラの言動があるメールやLINE等
配偶者の具体的なモラハラ行為を書いたメール等を送り、それに対し、配偶者がそのような行為があったことを認める内容を返信した場合のメール等のやり取りも証拠となり得ます。
・ 受けたモラハラの内容を記載した日記やメモ
・ 医師の診断書、診療記録等
・ 警察、自治体等の公的支援機関への相談記録
・ モラハラを目撃した第三者の証言等
○慰謝料請求の手続き
〈法律の専門家への相談〉
慰謝料請求を考えたら、まず専門家に相談するのが良いでしょう。
離婚を切り出した後や別居した後では、証拠を確保することが難しくなります。
相談する時期が早いほど適切な準備を行うことが可能となります。離婚や慰謝料の請求には、証拠が重要ですし、その証拠は離婚を切り出す前や別居の前に確保する必要があります。
早い時期から弁護士に相談して準備をすることが、希望する条件での離婚や離婚後の安定した生活につながります。
〈夫婦間の協議〉
夫婦での話し合いが難しい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士から相手方に対し、今後は弁護士が代理人として交渉を行うことを連絡し、話し合いの窓口を弁護士に一本化します。
〈離婚調停〉
離婚と慰謝料について、離婚調停で話し合うことができます。
婚姻費用分担調停とあわせて離婚調停を申し立てることも少なくありません。
離婚調停では、財産分与、親権、養育費、年金分割などについても話し合います。
〈離婚裁判〉
調停で合意できなかった場合、離婚裁判で離婚請求とあわせて慰謝料を請求することができます。
離婚前または離婚後に慰謝料を請求する裁判(訴訟)を提起することもできます。
モラハラ離婚における子どもの親権
○親権を決める基準
一般的に、家庭裁判所は、子どもの福祉(利益)を最優先に考えます。親権者の決定においては、以下のような要素が考慮されます。
・監護の継続性・主たる監護者 現実に子どもを養育監護している親が優先される傾向があります。監護養育を行ってきた親との関係を切り離すことは、子どもを不安にさせ、継続的な心理的不安定をもたらすおそれがあるからです。また、生活環境の変化は子どもに大きなストレスを与えます。そのため、これまで主に子育てを担当してきた親、同居している親が優先される傾向にあります。 それまでの監護が不適切で、子どもに悪影響を与えていれば、不利な事情として考慮されて、監護していない親が親権者となる場合もあります。
・子どもの意思
15歳以上の子についてはその意思が尊重されます。
10歳から14歳の子について、その子の意思が反映されます。
・兄弟姉妹関係の尊重
兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に影響を及ぼすため、また、兄弟姉妹が一緒に生活することで得られる体験が人格形成において貴重であることから、兄弟姉妹はなるべく分離しない方が良いと考えられています。兄弟姉妹が別々に生活している状況が続いている場合や子どもの年齢、子どもの意向などから、兄弟姉妹の親権者が父母で分離することもあります。
・浮気等の婚姻破綻についての有責性
例えば、浮気が原因で離婚となった場合、浮気が子どもの監護養育に直接影響を与えるとは考えられておらず、離婚への有責性は親権者の判断に直結するものではありません。
浮気等の結果、子どもの監護養育がないがしろにされて、子どもの監護養育に悪影響を与えている場合は、親権者の判断において考慮されると考えられます。
・面会交流への姿勢
離婚後も、子どもが同居していない親と継続的に交流の機会を持つことにより、父母両方から愛情を受けられる環境を整えることは、子どもの成長にとってとても大切なことです。一般的には、面会交流に拒否的な態度だけを理由として親権者として不適格であると判断される事案は少ないと思われますが、面会交流を実施する姿勢を持っていることは、補充的に考慮されると考えられます。
・子の奪取の違法性
父母のどちらかと安定した生活を送っている子どもを他方の親が違法に奪った場合、奪取した親は、親権者としての適格性に問題があるとされます。
・親族の協力・援助
本人だけでは十分な養育が困難であっても、親族の協力が得られる場合、その事情も補助的な事情として考慮されます。
・経済状態
収入が低いとしても、養育費等により、ある程度経済力は補うことができるため、他の判断要素と比べて重視されていないようです。
○モラハラ・精神的虐待が親権に与える影響
モラハラの事実が証明されると、モラハラをした親は、親権者の判断において不利になる可能性があります。特に、モラハラが子どもに悪影響を及ぼすと認められる場合、親権者を決める際に不利な事情として考慮されるでしょう。
ただ、モラハラの程度には軽重がありますし、モラハラの影響が子どもに対してどの程度及ぶのか等、事情も様々です。
モラハラ加害者から親権を争われた場合、弁護士に相談するのがよいでしょう。
〈子どもに対するモラハラ・精神的虐待がある場合〉
子どもに対するモラハラ・精神的虐待があれば、子どもにモラハラ・精神的虐待を行った親は、親権者としては不適格と判断され、親権者として選ばれる可能性は低いでしょう。
〈夫婦間でだけモラハラがあった場合〉
モラハラは夫婦間だけであり、子どもに対するモラハラ・精神的虐待がない場合はどうでしょうか。
この場合、配偶者に対するモラハラが子どもに対して影響を及ぼさない場合、モラハラの事実は親権者の判断に直結せず、モラハラ加害者が親権者となる可能性はあります。
他方、配偶者に対するモラハラが子どもにも悪影響を及ぼすと認められれば、モラハラの事実はモラハラ加害者にとって、親権者を決める際に不利に働く可能性があります。
〈モラハラが原因で子どもを連れて別居した場合〉
別居する際に合理的な理由もなく子どもを連れて別居した場合など、監護の開始に違法性があると判断される場合もあります。
たとえば、夫婦間で話し合いができたにもかかわらず、話し合うことを試みずに一方的に子どもを連れて別居した場合など、親権者の判断において不利な事情として考慮されるリスクはあります。
もっとも、別居前から主たる監護者として子どもを育てていた親が、配偶者のモラハラから逃れるために別居せざるをえず、子どもを連れて別居した場合、別居には正当な理由があるといえますし、子どもを連れていったことは違法とはいえないと考えられます。
具体的な状況によって判断が変わることがあります。お悩みがある場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。
○面会交流について
モラハラを理由に離婚する場合、面会交流について争いになる可能性があります。
モラハラ被害者の多くは、面会交流を拒否したいと考え、他方、モラハラ加害者は、子どもとの面会交流は当然認められると考えているケースは少なくありません。
面会交流を拒否したいというモラハラ被害者の気持ちも理解できます。
もっとも、面会交流は、子どもの健全な成長にとって有益であり、とても大切なことですので、子どもの福祉(利益)を害する場合に限って拒否することができると考えられます。
たとえば、子どもに対してもモラハラがあった場合で、子どもがモラハラ加害者である非監護親に恐怖心を抱いていたり、非監護親の名前を聞くだけで非監護親から受けた辛い体験を思い出して体調不良になるときには、面会交流が制限されるべきであると考えられます。また、子どもに対するモラハラはなかったが、子どもの目の前でモラハラが行われており、子どもがモラハラ加害者である非監護親に対して恐怖心を抱いている場合などでも、面会交流が制限される可能性があります。
モラハラ離婚で失敗しないためのポイント
○弁護士に相談する
モラハラを理由に離婚を検討されている場合、慎重な行動、事前の準備が求められます。適切に準備を進めるには、弁護士に相談することをおすすめします。
○モラハラ夫への対応
モラハラを行う配偶者への対応は、デリケートで難しい問題です。心身の安全を守るために、以下のような対応を検討するのがよいでしょう。
〈証拠の確保〉
離婚や慰謝料請求する場合に備えて、可能な範囲で、モラハラの内容や頻度を、記録・録音・録画するなどして証拠を残すことが重要です。証拠があれば、その後の話し合いや法的手続きに役立ちます。
また、適正な財産分与のために、配偶者の財産に関する情報・資料を収集することも大切です。
〈安全確保〉
身の安全が最優先です。暴力やエスカレートした行動がある場合は、すぐに安全な場所に避難し、必要に応じて警察や支援機関に連絡してください。
状況に応じて、別居についても検討しましょう。
〈専門家への相談〉
弁護士や心理カウンセラー、家庭問題に詳しい専門家に相談し、具体的なアドバイスや支援を受けることが重要です。特に、法的措置や離婚を検討している場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
〈支援団体や相談窓口の利用〉
DV・モラハラ被害者支援のための相談窓口や支援団体があります。これらの機関は、心理的サポートや避難場所の紹介などを行っています。お住まいの市区町村役場に相談するのがよいでしょう。
〈冷静な対応と距離の確保〉
可能な範囲で、感情的にならず、冷静に対応し、必要に応じて距離を取ることも有効です。感情的なやり取りは、状況を悪化させることがあります。当事者同士では、感情的になってしまうことが多いと思われます。離婚の話し合いについて、弁護士に交渉を任せるのがよいケースが多いでしょう。
〈法的措置の検討〉
継続的なモラハラや暴力がある場合、保護命令や離婚調停・訴訟など法的に対処することも選択肢となります。
○離婚後の生活設計
離婚により、生活に大きな変化・影響が生じます。
そのため、別居や離婚の前に、離婚後の生活設計をしておくことは、離婚そのものと同じくらい重要です。
まずは生活費の確保と住居の確保が重要な課題となることが少なくありません。
離婚後は、配偶者から生活費をもらうことはできませんので、収入の確保が大切です。特に、結婚して仕事をやめ、家庭に入った方は、財産分与、年金分割などで得られる金額を把握すること、安定した収入を得る方法を検討することが大切です。
〈財産分与〉
・財産分与とは
財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分け合うことです。
離婚時にどのくらい財産分与を受けることができるか検討することが大切です。
・財産分与の対象財産
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産です。
財産分与の対象となり得るものとして、次のものが挙げられます。
・預貯金
・不動産
・株式、投資信託
・自動車、宝飾品
・保険
・退職金など
別居後は経済的な協力関係がなくなっていると考えられることから、離婚前に別居している場合、別居時の財産が財産分与の対象となります。
結婚する前から持っていた財産は財産分与の対象にはなりません。
婚姻期間中に得た財産であっても、親から贈与された財産や相続した財産は、夫婦の協力により形成した財産ではありませんので、財産分与の対象になりません。
長年一緒に暮らしていても、配偶者のもっている財産について把握していない場合もあります。離婚を切り出すと、財産を隠されてしまうこともあり得ます。別居後に配偶者の財産を調べることは難しくなります。離婚を切り出す前に、また、別居する前に、配偶者のもっている財産について確認・調査しておきましょう。
・財産の分け方
財産の分け方として、基本的に、貢献度に応じて財産を分けるのが公平だと考えられています。
貢献度は基本的には50:50とされることが多いです。「2分の1ルール」と呼ばれることがあります。
財産分与は半分ずつと法律で決まっているわけではありません。
夫婦で合意すれば、50:50ではなく、自由に分けることができます。
具体的にどのように財産を分けるかが問題となる場合もあります。
現金・預金の場合には、簡単に分けることができますが、共有財産が自宅不動産だけの場合で、一方または双方が自宅不動産に住み続けることを希望する場合など、具体的な分け方についても話し合わなければならない場合があります。
夫婦の共有財産に家、自動車、家財道具、株などが含まれると、価値評価や分け方について、検討と話し合いが必要になります。
自宅不動産を購入する際に、親から頭金を出してもらっている場合や、結婚する前に貯めた預金から頭金を出した場合など、半分ずつで分けた結果が不公平になる場合もあります。
不動産など、価額を決めるために評価を必要とする財産もあります。
こういった分け方の話し合いや財産評価が必要になるなどの複雑な財産分与では、適正な財産分与をするために、法律知識と交渉力が必要となります。
離婚後に安定した生活を送るためにも適正な財産分与を行うことが重要です。
〈年金分割〉
年金分割は、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績を多い方から少ない方に分割する制度です。年金分割の結果、それぞれが受け取る年金額が変わります。
年金分割により自分が年金をどのくらいもらえることになるのかを確認することも大切です。50歳以上であれば、見込額の照会を希望すると、分割後の年金見込額を知ることができます。照会の手続きは年金事務所で行うことができます。
ただし、年金分割を受けて、もらえる年金の額が増えても、実際にお金がもらえるのは、ご自分が年金を受給し始めてからですので、年金を受給するまでにまだ時間がある場合は、生活費の確保について検討が必要です。
なお、年金分割の手続きは、離婚から2年以内にする必要があります。
〈慰謝料〉
慰謝料は、相手方の行為によって精神的苦痛を受けた場合に支払われる賠償金のことです。
離婚の際に慰謝料が必ず支払われると思われている方もおられるかもしれませんが、どんな場合でも請求できるわけではありません。
浮気や暴力などの不法行為がある場合は請求できます。しかし、性格の不一致が原因で離婚する場合など、相手に重大な落ち度や責任がない場合は慰謝料を請求することはできません。
離婚にあたって慰謝料を必ず請求できるわけではありませんので、請求できるかどうか事前の検討が必要です。
〈養育費〉
まだ自立していない子どもがいる場合には、離婚前に養育費について話し合い、決めることが大切です。
離婚後、子どもと一緒に暮らす親は、子どもと離れて暮らしている親に養育費を請求することができます。
養育費は、子どもが生活するために必要な費用(衣食住の費用、教育費、医療費、娯楽費など)のことです。
養育費の額は、基本的には、双方の収入を基準にして算定します。
裁判所が早見表(養育費算定表)を公開しており、調停や裁判になった場合、算定表に基づいて算出されることが多いです。
算定表は、あくまで標準的な額を簡易迅速に算定するためのものですので、個別事情をすべて考慮して作成されているわけではありません。個別事情を考慮した算定が必要な場合、弁護士に相談することをおすすめします。
養育費は、子どもの成長にとってとても重要なものであり、子どもが安定した生活を送るために、きちんと支払われることが大切です。
養育費について、金額だけでなく、支払方法・条件についても具体的に決めておきましょう。
離婚時の話し合いで養育費を決めることができる場合、約束した内容を書面にしておくことが大切です。
離婚後に安定した生活を送るために、適正な財産分与や年金分割等で財産・収入を確保できるように、一人で悩まず、弁護士に相談することをおすすめします。
モラハラ離婚に関するよくある質問
モラハラを証明するにはどうすればいいですか?
モラハラを証明するには、客観的な証拠を集めることが重要です。証拠として、次のものが挙げられます。
・録音、録画
モラハラ発言やモラハラ行動を記録することで、客観的な証拠、具体的な証拠を残すことができます
決定的な場面を記録できなくてもあきらめずに、多くの回数を記録するようにしましょう。記録できた回数が多くなれば、モラハラが長期間にわたっていたことや、モラハラ行為が繰り返し行われていたことの証拠となります。焦らずに、決定的な証拠を残すという姿勢よりも、小さくても数多くの証拠を残すという姿勢が良いでしょう。
・メールやLINE等のSNSのやり取り
モラハラ発言が書かれたメールやLINE等は、スクリーンショットとデータを保存して残しておきましょう。例えば、別居後のやり取りで、「家に戻ってこいと言うのなら、○○したことを謝ってほしい」とのメッセージを送ったところ、相手から「○○したのは**の理由からだ」という返事が来たとしたら、○○したことを認めているといえます。このようなやり取りも証拠となりますので、保存しておきましょう。
配偶者にスマホをチェックされたり、取り上げられる可能性がある場合は、協力してくれる親や友人に転送しておくと安心です。
すでに別居中である場合やすぐに自宅を出て避難しないと身に危険がある場合には、録音や録画は難しいかもしれません。そのような場合でも、あきらめないことが大切です。相手方がすぐにモラハラ行為をやめられないこともあります。別居後もモラハラの証拠を残す可能性があります。別居後に、メールやSNSで暴言が送られてくることや大量の着信を残すこともあるでしょう。メール等のやり取りで、モラハラ行為があったことが判明することもあります。あきらめないことが大切です。
・日記やメモ
日々のモラハラの内容を記録し、日時や状況、内容を詳細に、具体的に書き残しておくことでモラハラを証明することができる場合があります。
日記やメモについては、証拠価値が高いとはいえませんが、客観的な証拠を残すことが簡単ではない場合もあるでしょう。他の証拠とあわせることで、配偶者のモラハラ行為を証明できる場合もありますので、あきらめることなく、記録を残すことが大切です。
配偶者の暴言等のモラハラが日常的に行われている場合、その日時、暴言等の内容について記憶が明確でない場合も少なくありません。抽象的に「毎日暴言をはかれた」というだけでは、モラハラがあったことの主張・証拠として十分とはいえません。暴言等については、どのような表現、態様、場面で言われたか(行われたか)が重要です。
どのくらいの期間や頻度でモラハラがあったかも重要です。
日々のモラハラの日時、内容等を具体的に、できる限り詳しく、具体的に残しておきましょう。
・壊された物の写真
モラハラ行為の録画や録音ができなかった場合でも、物を壊すなどの行為があった場合、壊された物などの写真を撮っておくことも大切です。
・警察や公的機関への相談記録
公的機関に相談した記録が残っている場合、その記録を入手できれば証拠として使えることもあります。
・第三者の証言
モラハラは、家庭内で行われることが多いですが、家族や友人での面前でモラハラが行われることもあります。そのようなケースでは、モラハラを目撃した人の証言も証拠となりえます。
・診断書や通院履歴
配偶者のモラハラにより精神的に大きなダメージを受けたことについては、心療内科や精神科を受診して、診断書等により証明することが大切です。
証拠を集める際は、焦らず、あきらめることなく、安全を確保しながら行うことが大切です。
離婚せずにモラハラを止めさせる方法はありますか?
夫婦間でのモラハラは、夫婦という関係を基礎として行われますので、モラハラを止めさせる方法としては、夫婦関係の解消、つまり離婚が最も効果的です。
離婚が最も効果的であるとはいっても、子どものことなどを考えて、離婚以外の方法での解決を望まれる方もおられるでしょう。また、離婚後の生活等が不安で、すぐに離婚することが難しいという方もおられるでしょう。
モラハラの根本的な解決には時間と気力が必要ですが、以下のような対策を取ることで改善を図ることが可能な場合もあります。
・相手に気持ちを伝える
配偶者自身がモラハラをしていることに気づいていない場合は、冷静に話し合い、相手の具体的な言動がどのような影響を与えているかを伝えることで関係が改善されることがあります。
・専門家のカウンセリングの利用
心理カウンセラー等の専門家に相談し、モラハラの原因を探り、コミュニケーションの改善を図ることが考えられます。第三者の専門的な視点からアドバイスを受けることで、関係の改善が期待できる場合もあります。
・支援ネットワークの構築
家族や友人、支援団体など、信頼できる人々に状況を話し、サポートを受けることも重要です。孤立しないことが、問題解決の助けとなります。
・法的措置や制度の活用
モラハラをする人は価値観や考え方に強いこだわりを持っていることが多いため、モラハラが改善しない場合やエスカレートする場合もあるでしょう。
改善しない場合やエスカレートした場合は、法的な対応を検討することが大切です。
この場合は、安心して過ごせる環境を作り、自分らしい人生を送るため、離婚を検討することも必要だと思います。
モラハラ夫から逃げるにはどうすればいいですか?
モラハラを行う配偶者から安全に逃れるためには、計画的かつ慎重に行動することが重要です。
〈証拠を集める〉
モラハラの証拠を集めておくことで、後々の法的手続きがスムーズになり、役立ちます。具体的には、以下の証拠が考えられます。
①モラハラの発言等を録音・録画する
②メール、LINE等のSNSのメッセージを保存する。モラハラの内容だけでなく、頻度も重要となりますので、いつのメッセージであるか分かるように保存しましょう。
③日記やメモに記録する。
いつ、どのような言動があったのか、具体的な出来事を記録しましょう。
④医師の診断書、診療記録等
モラハラを受け、ストレスから、食欲不振、無気力、不眠などといった症状が現れることがあります。抑うつ状態(気分が落ち込み、憂鬱な気持ちが続く状態)、うつ病、適応障害などになることもあります。
そのような場合は、通院し、医師の診断書を取得します。
医師の診断書や診療記録で、配偶者によるモラハラ行為を証明することは難しいですが、あなたの心身が復縁できるような状態ではないことを、相手方や裁判所に説明・説得する資料となります。
⑤警察や公的な機関への相談記録
警察や公的機関(自治体の相談センター等)にモラハラの相談をした事実も証拠となる場合があります。公的機関に相談した内容が書面で保管され、その写しを取得することができれば、日記やメモ等の記録や他の証拠と組み合わせて、モラハラの事実を証明することができる場合もあります。
⑥第三者の証言等
モラハラを目撃した人の証言も証拠となり得ます。
〈安全な場所の確保〉
安全な場所(可能であれば相手に知られない場所)を確保します。
・実家、親戚宅
・信頼できる友人宅
・シェルターや支援施設
・賃貸住宅
〈専門家・専門機関への相談〉
法律の専門家や支援機関に相談することで、適切なアドバイスが受けられます。
相談先として、
・弁護士(主に、離婚や慰謝料請求の相談)
・DV・モラハラ相談窓口(避難や支援の相談)
・警察(緊急時の対応等)
〈生活の準備〉
別居後の生活を安定させるため、以下の準備をしておくと安心です。
・預貯金等の生活費の確保
・収入源の確保(仕事を探す、支援制度を利用する)
・婚姻費用の請求
〈別居の実行〉
必要な荷物を準備しておきましょう。
身の安全のために、最低限の衣類や生活必需品をまとめておくとよいでしょう。
重要な書類(身分証明書、保険証、通帳、子どもの健康保険証など)も忘れずに。
別居の方法として、事前に話し合って別居する方法と、事前に告げずに別居する方法があります。
モラハラの程度によっては、安全のために、相手方に知らせずに別居する方法を選択します。
安全が最優先です。1人で悩まずに、早めに弁護士等の専門家に相談し、支援を受けながら進めるのが良いでしょう。
まとめ
配偶者の言動や態度より辛さや悩みを感じたら、親や友人だけでなく、弁護士などの専門家に相談し、サポートを受けることが大切です。
モラハラを受けているかもしれないと感じたら、第三者に相談しましょう。モラハラを受けているけど、どうしたらいいかわからないという方もおられるでしょう。一人で悩まず相談することが大切です。
状況や話し合いの結果によっては、自分らしい人生を送るために、環境を変えるという選択をする必要があるかもしれません。
モラハラを受けた方が離婚に向けて一歩を踏み出すことは大きな決断であり、勇気のいることです。 また、相手がモラハラ配偶者ですので、離婚までの道のりには困難もあると予想されます。
一人で悩まず、協力を得て対処するのがよいでしょう。
離婚や別居を考えている方は、お気軽にご相談ください。