離婚したいけど、離婚後の生活費が心配。
別居したいけど、経済的な不安を感じる。
このような心配・不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
特に、結婚した後や子どもを出産した後に仕事を辞めた方にとっては、配偶者から生活費がもらえなくなると生活できなくなると心配になる方も多いでしょう。
子どもがいる場合は、いっそう不安を感じていることと思います。
このページでは、別居後、離婚後、それぞれの場合にもらえるお金・財産、公的支援について説明します。
別居中の婚姻費用、支援(公的制度)
婚姻費用
〈婚姻費用とは〉
婚姻費用とは、衣食住の日常の生活費、教育費、医療費、交際費など婚姻生活を営むのに必要な費用のことです。婚姻費用には、未成熟子の養育費も含まれます。なお、未成熟子とは、経済的に独立していない子どもですので、未成年と同じではありません。たとえば、成年に達していても大学生の子どもは未成熟子にあたる場合があります。
夫婦には互いに協力して扶助する義務がありますので、離婚の協議中、調停中、別居中であったとしても、夫婦は、婚姻費用を分担することになります。離婚が成立するまで、婚姻費用(生活費)を分担しなければなりません。
〈婚姻費用の算定〉
一般的には、夫婦間で収入の少ない方が多い方に婚姻費用を請求します。
婚姻費用の金額については、家庭裁判所で使用されている「養育費・婚姻費用算定表」を参考にすることができます。
「算定表」は簡易迅速に婚姻費用を算出するために標準的な事情を考慮して作成されていますが、個別事情をすべて考慮して作成されているわけではありません。
たとえば、学費・学習塾の費用について、「算定表」では、公立学校・公立高等学校に関する学校教育費を考慮していますが、私立学校に通っている場合や学習塾の費用等については考慮していません。配偶者が別居前に子どもが私立学校に進学することを了解していた場合など、配偶者に私立学校の学費等について分担請求することができる場合があります。
算定表そのままではなく、個別事情を加味しての算定が必要なケースもありますので、婚姻費用の算定について、弁護士に相談することをおすすめします。
婚姻費用の請求が認められないケースもあります。
別居の原因を作った人は婚姻費用を請求できるでしょうか。
別居の原因によっては、自ら夫婦間の義務を怠っておきながら、相手方に対してだけ義務を果たすよう求めることが権利の濫用にあたるとして、婚姻費用を請求しても減額されたり、請求自体が認められないこともあります。
なお、別居した原因が一方的に妻又は夫にあるとしても、子どもに責任はありませんので、別居原因を作った側が子どもを連れて別居したとき、別居原因を作った側は婚姻費用の中の子どもの養育費に相当する分について請求することができます。
〈請求の仕方〉
まずは、夫婦間で話し合いを行います。
話し合いをしても相手が婚姻費用を払ってくれない場合、話し合いが難しい場合は、婚姻費用の分担を求めて調停を申し立てるのがよいでしょう。
基本的に、調停や審判の実務では、婚姻費用の支払を請求した時(通常は、婚姻費用の支払を求める調停や審判を家庭裁判所に申し立てた時)から支払義務が生じると考えられていますので、話し合いでの合意が難しい場合には、速やかに調停を申し立てるのがよいでしょう。
婚姻費用分担調停が不成立となった場合、審判に移行します。
審判では、裁判官が事情を考慮して決定を出します。
調停でも審判でも、個別事情については、適切に主張し、資料を提出することが重要です。
〈婚姻費用を請求できる期間〉
離婚が成立すると、婚姻費用の支払いは終了します。
離婚する際は、収入・資産(財産分与、慰謝料、預貯金、離婚後の収入等)と支出(離婚後にかかる生活費等)を確認、検討し、タイミング・時期を考えることが大切です。
支援(公的制度)
別居中に受けられる支援があります。
〈児童手当〉
・支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方
・支給額(一人あたりの月額)
3歳未満 1万5000円(第3子以降は3万円)
3歳以上高校生年代 1万円(第3子以降は3万円)
・離婚協議中で配偶者と別居している場合
離婚協議中である事実を確認できる資料(調停期日呼出状の写し、家庭裁判所の事件係属証明書、調停不成立証明書など)を市区町村役場に提出し、児童手当の認定請求を行うことで、児童と住所が同じ親が児童手当を受給することができます(こども家庭庁 児童手当Q&A参照)
・配偶者から暴力を受けたため、住民票を移せない場合
配偶者に住所を知られることで危害を加えられるおそれがある場合など、やむを得ず住民票の異動ができない場合、①配偶者からの暴力について確認できる資料と②申請者と子どもが社会保険上、配偶者の扶養に入っていない(または申請者と子どものみ国民健康保険に加入しているなど)ことがわかる資料を提出することなどにより、住民票を移さなくても、児童手当を受給することができます(こども家庭庁 児童手当Q&A参照)
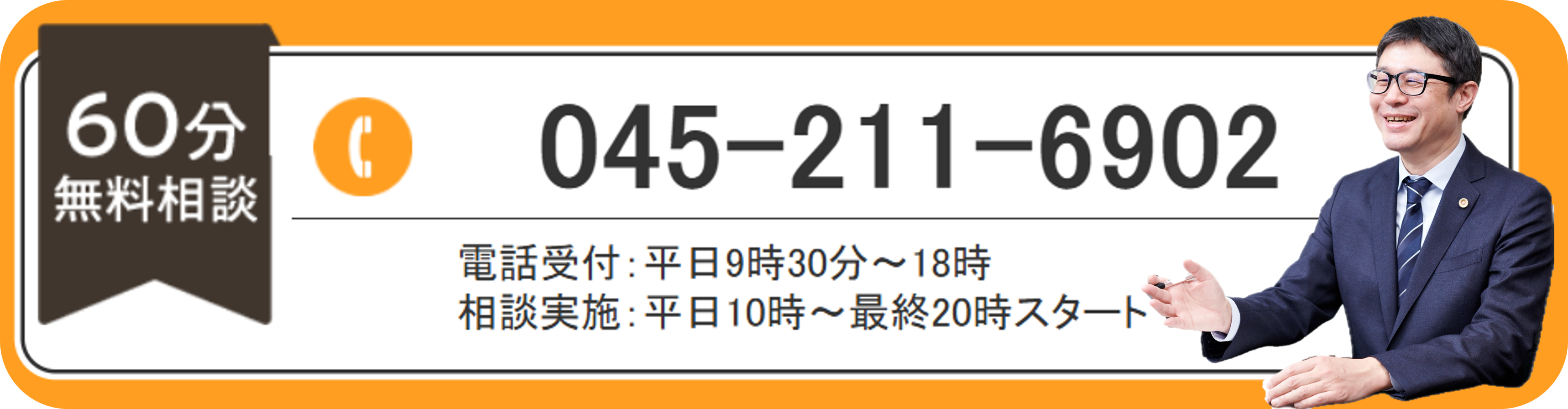
離婚にあたって受け取れるお金・財産について
財産分与
〈財産分与とは〉
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分けることです。
〈財産分与の対象となる財産〉
「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産」が対象になります。
名義は問われません。相手方の名義であっても、婚姻中に夫婦が協力して形成・維持してきた財産であれば、財産分与の対象となる夫婦共有財産にあたります。
現金・預金、不動産、自動車、株式、投資信託、退職金、保険(解約返戻金)などです。不動産等、その価値を評価することが必要な財産もあります。
別居後は経済的な協力関係がなくなっていると考えられることから、離婚前に別居が先行しているケースでは、通常、別居時の財産が財産分与の対象となります。
結婚前の財産(結婚前に貯めた預金など)は財産分与の対象にはなりません。贈与や相続により取得した財産も、夫婦の協力により築いた財産ではありませんので、財産分与の対象になりません。
配偶者がどのような財産を持っているか分からない場合も多いでしょう。相手方の財産については、教えてもらっている財産以外にも財産がないか、確認・検討する必要があります。
離婚を切り出した後や別居後に、配偶者の財産を調査することには限界がありますので、離婚を切り出す前や別居前に、配偶者の財産を把握しておくのがよいでしょう。
銀行、証券会社、保険会社から郵便物が届いているか確認することも大切です。郵便が届いている銀行等に財産がある可能性があります。
〈財産の分け方〉
財産分与の割合は基本的には2分の1です。
ただ、財産分与は半分ずつと法律で決まっているわけではありません。
お互いの合意があれば、50:50ではなく、自由に分けることができます。
交渉次第では、2分の1よりも多くもらえる可能性もあります。
財産分与の対象となる財産が現金・預金だけの場合には、簡単に分けることができます。
夫婦の共有財産に不動産、自動車、株式など、色々なものが含まれると、価格評価や分け方について、検討と話し合いが必要になります。
自宅不動産を購入する際に、親から頭金を出してもらっている場合や、結婚する前に貯めた預金から頭金を出した場合など、半分ずつで分けた結果が不公平になる場合もあります。
不動産など、価額を決めるために評価を必要とする財産もあります。
適正な財産分与を行うには、法律知識や交渉力が必要になります。
---民法改正---
2024年5月に民法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。この改正民法は2026年5月までに施行予定です。
この改正民法では、「婚姻中の財産の取得又は維持についての買う当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」と定められています(改正後民法768条3項)。
この改正民法では、財産分与を判断する際の考慮事情として、次のとおり明示しています。
① 当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額
② その取得又は維持についての各当事者の寄与の程度
③ 婚姻の期間
④ 婚姻中の生活水準
⑤ 婚姻中の協力及び扶助の状況
⑥ 各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入
⑦ その他の一切の事情
〈扶養的財産分与〉
財産分与には、3つの要素があると考えられています。
①夫婦共有財産を分け合う「清算的財産分与」、②離婚後の扶養のための「扶養的財産分与」、それと③「慰謝料的財産分与」です。
裁判所の実務では、財産分与については、まず清算的財産分与を検討し、清算的財産分与や離婚に伴う慰謝料などでは不十分な場合に扶養的要素が検討される傾向があります。
妻が結婚を機に退職し、長年にわたり家事・育児をして家庭を支えたという夫婦は少なくありません。離婚後は、婚姻費用(生活費)を請求することはできませんので、仕事を辞めた妻は、離婚後は自分で生活していかなければいけません。しかし、離婚後、妻がすぐに経済的に安定した生活をするだけの収入が得られる就職先を見つけることができないことも多いと思われます。
その一方で、夫は、離婚後も引き続き仕事を続ければ、これまでと同様の生活を送ることもできますが、夫が仕事を続けて稼げるようになったのは、自らの努力や才能だけではなく、妻が家事・育児をして夫が働ける環境を整えてきたからでもあります。
そうであれば、離婚後であっても、仕事をしている夫が妻をある程度扶養することが公平であるという考え方が扶養的財産分与です。
改正民法768条3項にある⑤婚姻中の協力及び扶助の状況、⑥各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入などは扶養的財産分与に関係する事情と考えられます。
〈財産分与の流れ〉
財産分与は、まずは話し合いにより決めることになります。
話し合いがまとまらない場合は、調停や裁判に移行します。
離婚時に財産分与について決めていなかった場合、離婚後も2年以内(改正民法の施行後は5年以内)であれば財産分与を請求することができます。
離婚後に請求した場合、話し合いを有利に進めることが難しくなったり、もらえるはずの財産がもらえない事態が生じる可能性があります。
離婚後に安定した生活を送るためにも、離婚前に財産分与について取り決めておきましょう。
慰謝料
〈慰謝料とは〉
慰謝料は、相手方の不法行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求できる賠償金のことです。
離婚の際に必ず支払われるものではなく、どんな場合でも請求できるわけではありません。
配偶者に、浮気や暴力などの不法行為がある場合に請求できます。
単なる性格の不一致が原因で離婚する場合など、相手に重大な落ち度や責任がない場合は慰謝料を請求することはできません。
また、夫から妻に支払われるものでもありません。妻が離婚の原因を作ったのであれば、妻から夫に慰謝料を支払う場合もあります。
〈慰謝料請求には証拠が重要〉
たとえば、相手が不貞行為やDV、モラハラを認めない場合、相手の不貞行為やDV、モラハラがあったことについて、慰謝料を請求する側が証明する必要があります。
証明するためには証拠が重要です。
証拠は、離婚を切り出す前や別居前に集めておくことが重要です。
〈慰謝料の相場〉
慰謝料の額は、事情や証拠の有無によって異なります。証拠がなければ、慰謝料が認められないこともあります。
裁判所で認められる慰謝料は、300万円程度までの範囲にとどまることが多いようです。
相場は裁判所の判決で認められている慰謝料の額に関する相場です。
協議(話し合い)の中で決めるのであれば、慰謝料の額は、夫婦双方が合意した金額となります。
養育費
〈養育費とは〉
養育費は、子どもと一緒に住んでいない親(別居親)が、子どもと同居して養育している親に支払う子どもの生活費です。
養育費には、子どもが生活するために必要な衣食住の費用、教育費、医療費、娯楽費などが含まれます。
家庭裁判所で使われている早見表(養育費算定表)が公表されていますので、参考にすることができます。
養育費算定表は、標準的な額を簡易迅速に算定するためのものですので、個別事情をすべて考慮して作成されているわけではありません。
たとえば、学費・学習塾の費用について、「算定表」では、公立学校・公立高等学校に関する学校教育費を考慮していますが、私立学校に通っている場合や学習塾の費用等については考慮していません。子どもが私立学校に進学することを相手方が承諾していた場合など、相手方に私立学校の学費等について請求することができる場合があります。
算定表そのままではなく、個別事情を加味しての検討、算定が必要なケースもありますので、養育費の算定について、弁護士に相談することをおすすめします。
〈請求方法〉
夫婦間で話し合いを行います。
話し合いで養育費を決めることができない場合、調停や審判等で決めることになります。
調停等では、個別事情については、適切に主張等することが重要です。
養育費は、離婚時に取り決めをしなかった場合でも、離婚後に請求することができます。
〈合意した内容を書面として残す〉
話し合いで養育費を決めた場合、合意した内容を書面にしておくことが大切です。将来的な不払いに備え、強制執行(差押え)ができるように、取り決めた内容を公正証書にしておくのがよいでしょう。
年金分割
年金分割は、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績を多い方から少ない方に分割する制度です。
公的年金には「国民年金」と「厚生年金」がありますが、分割できるのは厚生年金部分(旧共済年金を含む)です。
年金分割の結果、それぞれが受け取る年金額が変わります。配偶者より給料が低かった場合や専業主婦の場合、年金分割をすると、年金を受け取るときに加算されるため、年金分割は離婚後の重要な財産といえます。
合意分割をする場合、分割割合を決めるために、分割の対象となる期間やその期間における夫婦双方の情報を把握する必要がありますので、「年金分割のための情報通知書」を年金事務所等で入手します。
50歳以上であれば、見込額の照会を希望すると、分割後の年金見込額を知ることができます。照会の手続きは年金事務所で行うことができます。
なお、離婚から2年を経過すると年金分割の請求ができなくなります。年金分割の手続きは、離婚から2年以内にする必要があることに注意しましょう。
公的支援
離婚によって母子(父子)家庭になり、経済的に苦しくなってしまう方を援助する制度があります。
国が定めているものから市区町村などが行っている支援などがあります。詳しくは市区町村役場に確認しましょう。
ここでは代表的なものについていくつかご説明します。
〈児童扶養手当〉
・児童扶養手当は、父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等に支給される手当です。
・支給対象
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護する者
・支給要件
①父母が婚姻を解消した子ども
②父または母が死亡した子ども
③父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
④父または母の生死が明らかでない子ども
⑤父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
⑥父または母が1年以上遺棄している子ども
など
この他の支給要件もあり、支給要件を満たしているかどうかについて、お住まいの市区町村に確認しましょう
〈児童手当〉
・支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方
・支給額(一人あたりの月額)
3歳未満 1万5000円(第3子以降は3万円)
3歳以上高校生年代 1万円(第3子以降は3万円)
〈ひとり親家庭の家賃助成制度〉
市区町村独自の制度ですので、実施していない市区町村もあります。
支給の条件も市区町村によって異なりますので、お住まい(予定)の市区町村に確認が必要です。
〈医療費の助成〉
ひとり親家庭を対象とする医療費助成、こどもを対象とする医療費助成があります。市区町村が行っているものですので、助成内容や所得制限があるかなどについてお住まい(予定)の市区町村に確認が必要です。
〈母子父子寡婦福祉資金〉
母子家庭、父子家庭の人の自立支援のための貸付制度です。
資金の種類は、子どもの進学に必要な修学資金や就学支度資金などです。
貸付ですので、将来返済することになります。
詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。
〈寡婦・ひとり親控除〉
ひとり親家庭の親が子どもを扶養している場合、申告により所得控除が受けられます。
〈JR通勤定期割引制度〉
児童扶養手当を受けている世帯は通勤定期乗車券が3割引になる制度です。
〈バス・地下鉄等の特別乗車券交付(横浜市の場合)〉
児童扶養手当を受給している世帯等の方に、各区役所こども家庭支援課で、市営バス・民営バス(市外で乗車かつ降車する場合を除く)・市営地下鉄・金沢シーサイドラインの無料乗車券を交付しています(横浜市「バス・地下鉄等の特別乗車券について」参照)。詳しくは、区役所にお問い合わせください。
まとめ
別居中は、婚姻費用を請求することができます。
離婚後は、婚姻費用を請求することはできません。
離婚後の生活のため、財産分与、慰謝料、養育費等について取り決めておくようにしましょう。
本来もらえるはずの財産がもらえなかったということがないように、離婚や別居を考えた時点で、調査、証拠集めなど離婚条件の話し合いにむけた準備をすることが大切です。
どのようにして準備したらよいか不安がある方、お悩みの方は弁護士に相談することをおすすめします。


